NHK「お金もうけのジレンマ~新世代の資本主義論」を考える(中)
ナレーション:富を生む仕組みは時代とともに更新されていく。そのとき市場を動かす欲望も変わる。心の底に眠る欲望の形を見つめて。
社会学者D:人間の欲望というものは、もっと根源的というか、昔から身をきれいに飾りたいとか、いろんなものを所有したい、海外の美しい宝石がほしいというのは、資本主義どころか、何千年もの歴史があるわけじゃないですか。だから、もっと根源的に考えたほうがよくて、それ(欲望)をいちばんかなえてくれるものが資本主義なんですよ。Bさんは資本主義が始まった時代については詳しいのですが、資本主義というのは終わりそうなんですか?
→投稿者:資本主義を動かす原動力が個人的な「欲望」であるとして、個人的な問題に解消している。資本主義が「欲望」をかなえてくれるというが、資本間の競争原理にしたがって、コマーシャルで「欲望」を煽り、「欲望」が形成されている。
歴史学者B:かんたんには終わらないのじゃないか。人々が何がほしいとか、欲望をすごく巧みに駆動させるシステムとして、出来上がってきたという経緯が、少なくともここ500年ぐらいあるように感じていて、いきなりなくなるということはないんじゃないかな。
経済学者A:もうひとつ考えなければならない要因としては、エコロジーだと思います。欲望を突きつめていって、大量消費の社会ができて、資本主義を発展させていった。しかし自然は資本主義の理論とかけ離れたもので動いていて、温暖化などの側面を考慮に入れていかないと、生きていくこと自体が危ぶまれ、欲望などといっておれないと思う世代が出てきてもおかしくない。
→<欲望→大量消費→資本主義の発展>…「個人的欲望」が資本主義的生産関係の原動力であるかのように描いている。矮小ではないか。すでに肥大化し、巨大なシステムとして動いている資本主義を救済するために、「個人的な欲望」を抑制すればいいという方向で解決しようとしているのではないか? 温暖化、二酸化炭素の排出問題は資本に抑制的な行動を求める課題であり、資本の論理とは対立する。だから、日産、コベルコ、三菱などがデータをねつぞうし、不必要な費用がかからないようにしている。
社会学者D:資本主義体制下で生きる人はそんなバカじゃないから二酸化炭素の排出量を減らしましょうとか、折り合いをつけてやって来ているように思いますが、それでもまだ足りないですか。
経済学者A:不十分です。
→投稿者:十分か、不十分かの問題ではなく、資本主義自身が利潤追求過程で、「環境破壊」「温暖化」「二酸化炭素問題」を生み出してきたのであり、資本主義のシステムそのものに欠点があることを見なければならない。利潤追求を第1義にする資本(主義)に抜本的な解決を期待出来るはずがない。
起業家C:ぼくらの欲望が進化する大事な時期にきていると思います。なぜかというと、インターネットが登場してきたことによって、利他的な行動が瞬時に可視化される状態になっている。歴史的に見て大事なことだと思います。この収録のあと、Dさんが車にひかれそうな少年を救ったら、誰かが動画を撮っていて、ツイッターで拡散して、利他的な行動をとったDさんの社会的な価値を上げますね。マーク・ザッカーバーグ(フェイスブックのCEO)は宝石を買ったりしないじゃないですか、インターネットを可視化するという行動が大事だと思っていて、さらにその行動を加速させたいと思っているでしょう。
→投稿者:資本主義下で発生した「環境問題」について議論が始まったばかりなのに、議論を詰めもせずに、突然話題を変化させている。編集に恣意的なものを感じる。「欲望の進化」というが、技術革新によって齎されたインターネットに対応した「欲望」の創出であり、進化ではなく、変化にしか過ぎない。新たな環境のもとで利潤を生み出し、収奪しているだけだ。
社会学者D:賞賛されにくい行動は起こされにくい。街で交通事故から救うようなわかりやすい行動は評価されるけれども、評価されにくい行動、いかにも貧困者ではない人が貧困者を助けるのは、多分賞賛されにくいが、それでも救われる人が出て来るが、…。
歴史学者B:それは結局ビジネスとして、「共感」ビジネスになってしまうのじゃないですか。光と影の影の部分じゃないですか?
司会者E:「共感」って、時代によってどんどん変わって、不安定なものなんじゃないですか?
社会学者D:曖昧なものをベースにして、社会を作っていくと、確かに不安定さがありますね。
起業家C:確かに定義しにくいですね。「共感」という言葉のなかに、好きとか、感情移入とか、マインドシェア(あるブランドが消費者の心の中で占める割合)が奪われるとか、細かいものがまとめて入っていて、それを「共感」といっているんですよ。
→投稿者:論理的に定義もできないようなターム「共感」に基づいて議論するほど無駄なことはない。貧困問題が階級社会での資本による収奪の問題として措定されていない。富裕層が貧困層を生み出していながら、「救済」によって「解決」するのを可としている。まさに欺瞞である。
経済学者A:最近よく言われるのはアテンションエコノミー(興味、関心が価値を生み、交換材となる経済)で炎上させて、数さえ稼げれば、それでいいんだ。それが企業の儲けとか、知名度の向上に繋がる…。
歴史学者B:「反感」を集めることによっても、「共感」を集めることによっても、同じくビジネスはまわるかもしれないが、どういうふうにそれを…。
経済学者A:テイク(映画・音楽などで、一回分の撮影・録音)とかで注目を集めれば、アテンションエコノミーになる―そうなると、なんでも注目されればそれでいいとなり、信頼とか真理がどんどん揺らいで来ちゃって、さらに民主主義的なものも揺らいでいく。
→投稿者:要するに、「共感ビジネス」など、現代社会(インターネット社会)のあぶくみたいなもので、生まれたり、弾けたりして、過ぎ去っていく程度のものなのに、現代人はそれに振り回されている。
ナレーション:新春の「欲望の資本主義2018年」で、とりわけ大きな反響を呼んだのは、気鋭の哲学者の言葉だった。マルクス・ガブリエル(1980年生まれ)「資本主義は見世物だ。トランプはその象徴だ。今日の資本主義の世界はいわば商品の生産そのものになった。そもそも生産するとは何か?語源は『前に(pro)持って来る(duce)』だ。つまり商品の生産とは、いわば見せるための『ショウ』なのだ。今のアメリカの政権が富を生み出す方法はまさしくショウ形式によるものだ。
(テロップ―フェイクさえ商品になる―)
フェイクニュースのような偽物があふれている理由の一つは、大量生産がなされる状況において、おそらく偽物が理想的な商品だからだ。ベストな商品は安く作れて、浮ついたものなんだ。
(テロップ―『成功ファースト』の資本主義―)
iPhoneを発明しても、同じiPhoneを作り続けてもダメだろう?成功者でいるためには何かを達成するだけでなく、絶えず成功し続け、自ら維持する必要がある。これまで見えていなかったものに、目を向けるのだ。新たに『存在』を見つけ、値段をつける」
経済学者A:資本主義がたえず新しいものを生み続けなければならないという点に関していうと、技術革新の余裕もない状況なんです。そうすると新しい商品が出なくなって、資本主義が行き詰まってくる。
社会学者D:そういうなかで、「共感」というものまで商品化されちゃうのはいいんですかね。
経済学者A:「共感」をビジネスにすることで、(行き詰まりが)一時的に先延ばしになっていると思う。車とか、iPhoneなどに比べたら、雇用するニーズも全然違うし、そこで動くお金も資本主義の観点から見て全然小さいと思うので、行き詰まりは早晩来ると思います。
→投稿者:「共感ビジネス」の行き詰まり程度で、資本主義が行き詰まるなどというのはマンガ的ではないか? 確かに上位にはインターネット関係の資本家が並んでいるが、資本主義の本体は、旧来のモノづくりにあるだろう。
歴史学者B:歴史的に振り返ってみて、そもそも資本主義は何を目的にして、機能を果たしてきたのかを考えると、例えば、事業している人だけでは解決出来ない資本を集めねばならない問題があって、それをそのときどきに解決してきたと見ることができる。だとしたら、いま、自然環境を考えないと、危機的な状況になり、それを解決するときにどういうふうにビジネスチャンスに変えることができるか。
経済学者A:資本主義のもとで、ビジネスはいろんなイノベーションを起こしてきたことは事実だと思いますが、それがある程度まで行くと、さらなるイノベーション、さらなる協働関係を作り出すための足枷になる。特許はそうなっています。
歴史学者B:そうすると自然環境保護にしても、温暖化対策にしても、技術者が活かしていきたいと思っても、競争している会社間で互いに足を引っ張り合うということですか。
経済学者A:資本主義時代で、本当に発展させたかったら、オープンソースとかで、フリーにシェアしてゆけば、できる製品も安くなるが利潤は上げられなくなる。利潤を上げようとしたら、独占しなければならない。しかし、問題を解決するためには協働しなければならない。
社会学者D:このジレンマ(独占と協働)は資本主義の枠内のものなんですか?
歴史学者B:ぼくは資本主義の枠内のものだと感じています。
経済学者A:まったく新しいものというよりも、昔からあるものの変形ですか?
歴史学者B:そうですね。
経済学者A:いままで、新聞を買ったり、本を買ったり、CDを買わなければならなかったのに、コピーされて、一瞬でまったく同じクオリティのものが、ダダで拡散していくことになったら、CD会社もジャーナリズムも脅かされてしまうので、既存のモデルがどんどん壊れていく。
社会学者D:それでも音楽業界はCDの売り上げがなくなっても、ライブを増やし、お金儲けのシステムはまわっているわけで、形態が変わっているだけじゃないですか?
(テロップ―モノからコトへ?―)
起業家C:イノベーションと呼べるほどの市場規模にはならないが、ライブエンターテインメントはそれほど大きくはない。東京ドームとか、日本におけるライブの箱には数に限りがあり、ライブできる回数にも限りがあって、スケールは小さい。
→投稿者:エンタメは疎外労働を強いられている労働者に一時的に癒やしを与える産業である。資本による抑圧と収奪に伴う苦痛からの一時的な逃亡の場である。基幹産業の周縁に発生するあぶくのような産業である。
社会学者D:お金で見るとそれくらいのスケールなんだけど、違う何かが確実にある。
起業家C:それは可処分精神ということです。企業はサービスで奪い合って進化を遂げてきた。50年ぐらい前から奪い合いの歴史を見ると、可処分所得の奪い合いですね。テレビをメーカーが作って、消費者に選択してもらうという可処分所得の奪い合い。その次に、20年ぐらい前からインターネットが出てきて、グーグルとヤフーのどっちに時間を使うかという可処分時間の奪い合いに移っていった。それが今日まで続いています。お金って増やすことができるけれども、時間は増やせないから、時間の方が価値が大きいのじゃないですか。富豪上位の人たちって、可処分時間を奪いまくっている人たちです。次は何かと考えると、マインドエコノミー(定義は?)だとおもいます。可処分精神(定義は?)は何かに振り向ける限界があるから、100%の可処分精神を奪える主体が勝っていく。エンターテインメント、ライブ、映画は可処分精神を奪っている。
→投稿者:「時間は増やせない」というのは誤り。金沢―東京間を鈍行列車ではなく、新幹線で行くことによって、有効活用時間を「増やす」ことができる。また、資本家が労働者を雇用し、資本家のために働かせることによって、資本家は支配下の労働者の時間を所有(増やす)出来る。しかも、ここでは資本主義の根幹ではなく、「スケールの小さい」エンタメ業界のことしか議論していない。「マインドエコノミー」「可処分精神」はきちんと定義をしてから使用すべきである。
(テロップ―奪いあうもの―所得→時間→精神?
社会学者D:時間(?)を持っている会社の時価総額が高いというのはわかるのですが、マインドがお金になるというのはどういう状況ですか? 時間にしても、最近タイムワーク、個人の時間を切り売りするような会社が多いじゃないですか。時間まで商品になる資本主義は持続可能なんでしょうか?
経済学者A:持続可能じゃないでしょう。利子なども信用という時間を買っているという意味では、古典的な商品だと思う。こういうモデル自体は新しい商品を見つけることのむつかしさが、来るところまで来たんじゃないか。
社会学者D:業界は発展すると思っているんですか?
起業家C:可処分精神を正しく奪っている企業体やサービスやモノや人が永続的に繁栄すると思っています。その究極的な形は宗教です。
→投稿者:「宗教が永続的に繁栄する」との主張だが、宗教発生(発展)の歴史的関係性を認識していない。未発達な社会(自然の脅威を対象化出来なかった社会)で発生し、階級社会のなかで虐げられた人々の嘆きとして発展してきた宗教にたいする無理解が現れている。
経済学者A:それこそ商品生産からどんどん離れていく。
歴史学者B:その方がいいということですか?
経済学者A:そういう異質なモノ(可処分精神)を商品化することは、いままでのような資本主義の理解のモデルから、全然違うスキル(能力)に来ていて、お金儲けの手段に取り込んできている。わずか10年、20年のスパンでここまで変わってきたら、50年のスパンで考えたら、全然違う社会が…。
起業家C:そもそも経済の生産性をGDPで計れなくなる。
経済学者A:幸せになったり、コミュニケーションを取れるようになるかもしれないが、GDPという旧来の市場においては計れないものが…。
起業家C:幸せって、数値化して見えてこないんですよね。経済のなかで、それがある種再生数とかPV(ページビュー、閲覧された回数)に変換されて、そこに広告が付いて、広告市場でGDPが見えてくるかもしれないが、多分数値的に可視化しきれないところが多いと思います。
経済学者A:そこで可視化しきれない時間(?)がひとりひとりの人生とか、日々の日常において大きな意味を持つのか?
社会学者D:これは、ファシズムっぽくなりません? 宗教と商品が合体して、国家社会主義的なファシズムで、すごく気持ちが悪い社会になるんじゃないか? それでいいんですか?
歴史学者B:それは、脱中心的になっていくと…。
起業家C:それは多神教で、1個ではない。
経済学者A:危険性としては、プラットホームがフェイスブックだけ、グーグルだけになったら危ういところがあるけれども、分散させていけば…。
→投稿者:「神(商品)」が多数であろうが、単数であろうが、商品を「神」と例えた以上、人間は「神」に従属する存在(転倒した存在=自ら生み出しながら、それに従属する)であり、「(神)商品」を生み出した側(資本=支配階級)による支配(抑圧)に這いつくばることである。「商品=神」こそ、商品の本質的性格を表している。
起業家C:最近、トップページがない。ユーチューブだってトップページがない。
社会学者D:確かに。
起業家C:開いた瞬間に、猫の動画がたくさん出て来るじゃないですか。
社会学者D:その人のカスタマイズ(ユーザーの好みや使い勝手に合わせて、見た目や機能、構成といった製品の仕様を変更すること)されたものが出て。
起業家C:そうです。分散的で、多神教なんです。だから、ファシズムにはならない。猫好きのコミュニティみたいなものが無数に存在していて、そのなかで経済がまわる。
社会学者D:猫好きが猫のなかで、ズーッと暮らしていくのでいいんですか?
司会者E:内向きになっちゃいますね。
起業家C:そうですね。猫好きであり、時にはアニメ好きとか、いろんなコミュニティに同時に属するような感じです。抜けたり入ったりするのは自由です。
歴史学者B:いまの話しは、新しいように見えるが、資本主義のなかの光と影、その影の部分が気になります。ぼくもわからないが、一つ考えられるのは可処分時間を奪いあう、そのなかで「マインドエコノミー」というキーワードですが、人々の気持ちを奪いあう対象にしたいとなったときに、これまでだったら6時間、7時間眠れたのが、これもしたい、あれもしたいなどと時間がどんどん奪われていって、睡眠時間が減っていくのでは?
社会学者D:睡眠時間が減りそう。
歴史学者B:睡眠時間が減っていくことに関して、睡眠時間を守ることをビジネスにすることはあり得るんですか?
経済学者A:資本主義の力でしょうか、常に、どんなものが出てきても、ガブリエルの「異なるものを内に取り込んで商品化する」という力がある。
→投稿者:新たに起きた矛盾や問題を資本の運動で解決しようとする発想の貧困さにはウンザリする。労働者人民の自己解放性への期待のかけらもない。原発建設、運転、事故処理、廃炉をビジネスにし、労働者の健康を破壊し、資本が延命(肥大)していく。資本のあくどさの典型例。
社会学者D:全部売り物(商品)になって、その(資本主義)のグロテスクさがありますね。
起業家C:誰かに労働を指示されて、いやいや労働した結果、睡眠時間が削られるのではなく、猫の動画やAKBの動画を見たくて見たくてしょうがなく、それで睡眠時間が削られているから…。
歴史学者B:見たくてしょうがないんですかね?
社会学者D:そういうふうに駆動させられているともいえる。
→投稿者:食欲、性欲、睡眠は人間の内的な欲求であり、自己回復(労働力商品としての回復)のために必要な睡眠時間を削ってでも、AKBを見たいという欲望を煽る(再生産させ)る資本(コマーシャル)の破壊性。
ナレーション:富を生む仕組みは時代とともに更新されていく。そのとき市場を動かす欲望も変わる。心の底に眠る欲望の形を見つめて。
社会学者D:人間の欲望というものは、もっと根源的というか、昔から身をきれいに飾りたいとか、いろんなものを所有したい、海外の美しい宝石がほしいというのは、資本主義どころか、何千年もの歴史があるわけじゃないですか。だから、もっと根源的に考えたほうがよくて、それ(欲望)をいちばんかなえてくれるものが資本主義なんですよ。Bさんは資本主義が始まった時代については詳しいのですが、資本主義というのは終わりそうなんですか?
→投稿者:資本主義を動かす原動力が個人的な「欲望」であるとして、個人的な問題に解消している。資本主義が「欲望」をかなえてくれるというが、資本間の競争原理にしたがって、コマーシャルで「欲望」を煽り、「欲望」が形成されている。
歴史学者B:かんたんには終わらないのじゃないか。人々が何がほしいとか、欲望をすごく巧みに駆動させるシステムとして、出来上がってきたという経緯が、少なくともここ500年ぐらいあるように感じていて、いきなりなくなるということはないんじゃないかな。
経済学者A:もうひとつ考えなければならない要因としては、エコロジーだと思います。欲望を突きつめていって、大量消費の社会ができて、資本主義を発展させていった。しかし自然は資本主義の理論とかけ離れたもので動いていて、温暖化などの側面を考慮に入れていかないと、生きていくこと自体が危ぶまれ、欲望などといっておれないと思う世代が出てきてもおかしくない。
→<欲望→大量消費→資本主義の発展>…「個人的欲望」が資本主義的生産関係の原動力であるかのように描いている。矮小ではないか。すでに肥大化し、巨大なシステムとして動いている資本主義を救済するために、「個人的な欲望」を抑制すればいいという方向で解決しようとしているのではないか? 温暖化、二酸化炭素の排出問題は資本に抑制的な行動を求める課題であり、資本の論理とは対立する。だから、日産、コベルコ、三菱などがデータをねつぞうし、不必要な費用がかからないようにしている。
社会学者D:資本主義体制下で生きる人はそんなバカじゃないから二酸化炭素の排出量を減らしましょうとか、折り合いをつけてやって来ているように思いますが、それでもまだ足りないですか。
経済学者A:不十分です。
→投稿者:十分か、不十分かの問題ではなく、資本主義自身が利潤追求過程で、「環境破壊」「温暖化」「二酸化炭素問題」を生み出してきたのであり、資本主義のシステムそのものに欠点があることを見なければならない。利潤追求を第1義にする資本(主義)に抜本的な解決を期待出来るはずがない。
起業家C:ぼくらの欲望が進化する大事な時期にきていると思います。なぜかというと、インターネットが登場してきたことによって、利他的な行動が瞬時に可視化される状態になっている。歴史的に見て大事なことだと思います。この収録のあと、Dさんが車にひかれそうな少年を救ったら、誰かが動画を撮っていて、ツイッターで拡散して、利他的な行動をとったDさんの社会的な価値を上げますね。マーク・ザッカーバーグ(フェイスブックのCEO)は宝石を買ったりしないじゃないですか、インターネットを可視化するという行動が大事だと思っていて、さらにその行動を加速させたいと思っているでしょう。
→投稿者:資本主義下で発生した「環境問題」について議論が始まったばかりなのに、議論を詰めもせずに、突然話題を変化させている。編集に恣意的なものを感じる。「欲望の進化」というが、技術革新によって齎されたインターネットに対応した「欲望」の創出であり、進化ではなく、変化にしか過ぎない。新たな環境のもとで利潤を生み出し、収奪しているだけだ。
社会学者D:賞賛されにくい行動は起こされにくい。街で交通事故から救うようなわかりやすい行動は評価されるけれども、評価されにくい行動、いかにも貧困者ではない人が貧困者を助けるのは、多分賞賛されにくいが、それでも救われる人が出て来るが、…。
歴史学者B:それは結局ビジネスとして、「共感」ビジネスになってしまうのじゃないですか。光と影の影の部分じゃないですか?
司会者E:「共感」って、時代によってどんどん変わって、不安定なものなんじゃないですか?
社会学者D:曖昧なものをベースにして、社会を作っていくと、確かに不安定さがありますね。
起業家C:確かに定義しにくいですね。「共感」という言葉のなかに、好きとか、感情移入とか、マインドシェア(あるブランドが消費者の心の中で占める割合)が奪われるとか、細かいものがまとめて入っていて、それを「共感」といっているんですよ。
→投稿者:論理的に定義もできないようなターム「共感」に基づいて議論するほど無駄なことはない。貧困問題が階級社会での資本による収奪の問題として措定されていない。富裕層が貧困層を生み出していながら、「救済」によって「解決」するのを可としている。まさに欺瞞である。
経済学者A:最近よく言われるのはアテンションエコノミー(興味、関心が価値を生み、交換材となる経済)で炎上させて、数さえ稼げれば、それでいいんだ。それが企業の儲けとか、知名度の向上に繋がる…。
歴史学者B:「反感」を集めることによっても、「共感」を集めることによっても、同じくビジネスはまわるかもしれないが、どういうふうにそれを…。
経済学者A:テイク(映画・音楽などで、一回分の撮影・録音)とかで注目を集めれば、アテンションエコノミーになる―そうなると、なんでも注目されればそれでいいとなり、信頼とか真理がどんどん揺らいで来ちゃって、さらに民主主義的なものも揺らいでいく。
→投稿者:要するに、「共感ビジネス」など、現代社会(インターネット社会)のあぶくみたいなもので、生まれたり、弾けたりして、過ぎ去っていく程度のものなのに、現代人はそれに振り回されている。
ナレーション:新春の「欲望の資本主義2018年」で、とりわけ大きな反響を呼んだのは、気鋭の哲学者の言葉だった。マルクス・ガブリエル(1980年生まれ)「資本主義は見世物だ。トランプはその象徴だ。今日の資本主義の世界はいわば商品の生産そのものになった。そもそも生産するとは何か?語源は『前に(pro)持って来る(duce)』だ。つまり商品の生産とは、いわば見せるための『ショウ』なのだ。今のアメリカの政権が富を生み出す方法はまさしくショウ形式によるものだ。
(テロップ―フェイクさえ商品になる―)
フェイクニュースのような偽物があふれている理由の一つは、大量生産がなされる状況において、おそらく偽物が理想的な商品だからだ。ベストな商品は安く作れて、浮ついたものなんだ。
(テロップ―『成功ファースト』の資本主義―)
iPhoneを発明しても、同じiPhoneを作り続けてもダメだろう?成功者でいるためには何かを達成するだけでなく、絶えず成功し続け、自ら維持する必要がある。これまで見えていなかったものに、目を向けるのだ。新たに『存在』を見つけ、値段をつける」
経済学者A:資本主義がたえず新しいものを生み続けなければならないという点に関していうと、技術革新の余裕もない状況なんです。そうすると新しい商品が出なくなって、資本主義が行き詰まってくる。
社会学者D:そういうなかで、「共感」というものまで商品化されちゃうのはいいんですかね。
経済学者A:「共感」をビジネスにすることで、(行き詰まりが)一時的に先延ばしになっていると思う。車とか、iPhoneなどに比べたら、雇用するニーズも全然違うし、そこで動くお金も資本主義の観点から見て全然小さいと思うので、行き詰まりは早晩来ると思います。
→投稿者:「共感ビジネス」の行き詰まり程度で、資本主義が行き詰まるなどというのはマンガ的ではないか? 確かに上位にはインターネット関係の資本家が並んでいるが、資本主義の本体は、旧来のモノづくりにあるだろう。
歴史学者B:歴史的に振り返ってみて、そもそも資本主義は何を目的にして、機能を果たしてきたのかを考えると、例えば、事業している人だけでは解決出来ない資本を集めねばならない問題があって、それをそのときどきに解決してきたと見ることができる。だとしたら、いま、自然環境を考えないと、危機的な状況になり、それを解決するときにどういうふうにビジネスチャンスに変えることができるか。
経済学者A:資本主義のもとで、ビジネスはいろんなイノベーションを起こしてきたことは事実だと思いますが、それがある程度まで行くと、さらなるイノベーション、さらなる協働関係を作り出すための足枷になる。特許はそうなっています。
歴史学者B:そうすると自然環境保護にしても、温暖化対策にしても、技術者が活かしていきたいと思っても、競争している会社間で互いに足を引っ張り合うということですか。
経済学者A:資本主義時代で、本当に発展させたかったら、オープンソースとかで、フリーにシェアしてゆけば、できる製品も安くなるが利潤は上げられなくなる。利潤を上げようとしたら、独占しなければならない。しかし、問題を解決するためには協働しなければならない。
社会学者D:このジレンマ(独占と協働)は資本主義の枠内のものなんですか?
歴史学者B:ぼくは資本主義の枠内のものだと感じています。
経済学者A:まったく新しいものというよりも、昔からあるものの変形ですか?
歴史学者B:そうですね。
経済学者A:いままで、新聞を買ったり、本を買ったり、CDを買わなければならなかったのに、コピーされて、一瞬でまったく同じクオリティのものが、ダダで拡散していくことになったら、CD会社もジャーナリズムも脅かされてしまうので、既存のモデルがどんどん壊れていく。
社会学者D:それでも音楽業界はCDの売り上げがなくなっても、ライブを増やし、お金儲けのシステムはまわっているわけで、形態が変わっているだけじゃないですか?
(テロップ―モノからコトへ?―)
起業家C:イノベーションと呼べるほどの市場規模にはならないが、ライブエンターテインメントはそれほど大きくはない。東京ドームとか、日本におけるライブの箱には数に限りがあり、ライブできる回数にも限りがあって、スケールは小さい。
→投稿者:エンタメは疎外労働を強いられている労働者に一時的に癒やしを与える産業である。資本による抑圧と収奪に伴う苦痛からの一時的な逃亡の場である。基幹産業の周縁に発生するあぶくのような産業である。
社会学者D:お金で見るとそれくらいのスケールなんだけど、違う何かが確実にある。
起業家C:それは可処分精神ということです。企業はサービスで奪い合って進化を遂げてきた。50年ぐらい前から奪い合いの歴史を見ると、可処分所得の奪い合いですね。テレビをメーカーが作って、消費者に選択してもらうという可処分所得の奪い合い。その次に、20年ぐらい前からインターネットが出てきて、グーグルとヤフーのどっちに時間を使うかという可処分時間の奪い合いに移っていった。それが今日まで続いています。お金って増やすことができるけれども、時間は増やせないから、時間の方が価値が大きいのじゃないですか。富豪上位の人たちって、可処分時間を奪いまくっている人たちです。次は何かと考えると、マインドエコノミー(定義は?)だとおもいます。可処分精神(定義は?)は何かに振り向ける限界があるから、100%の可処分精神を奪える主体が勝っていく。エンターテインメント、ライブ、映画は可処分精神を奪っている。
→投稿者:「時間は増やせない」というのは誤り。金沢―東京間を鈍行列車ではなく、新幹線で行くことによって、有効活用時間を「増やす」ことができる。また、資本家が労働者を雇用し、資本家のために働かせることによって、資本家は支配下の労働者の時間を所有(増やす)出来る。しかも、ここでは資本主義の根幹ではなく、「スケールの小さい」エンタメ業界のことしか議論していない。「マインドエコノミー」「可処分精神」はきちんと定義をしてから使用すべきである。
(テロップ―奪いあうもの―所得→時間→精神?
社会学者D:時間(?)を持っている会社の時価総額が高いというのはわかるのですが、マインドがお金になるというのはどういう状況ですか? 時間にしても、最近タイムワーク、個人の時間を切り売りするような会社が多いじゃないですか。時間まで商品になる資本主義は持続可能なんでしょうか?
経済学者A:持続可能じゃないでしょう。利子なども信用という時間を買っているという意味では、古典的な商品だと思う。こういうモデル自体は新しい商品を見つけることのむつかしさが、来るところまで来たんじゃないか。
社会学者D:業界は発展すると思っているんですか?
起業家C:可処分精神を正しく奪っている企業体やサービスやモノや人が永続的に繁栄すると思っています。その究極的な形は宗教です。
→投稿者:「宗教が永続的に繁栄する」との主張だが、宗教発生(発展)の歴史的関係性を認識していない。未発達な社会(自然の脅威を対象化出来なかった社会)で発生し、階級社会のなかで虐げられた人々の嘆きとして発展してきた宗教にたいする無理解が現れている。
経済学者A:それこそ商品生産からどんどん離れていく。
歴史学者B:その方がいいということですか?
経済学者A:そういう異質なモノ(可処分精神)を商品化することは、いままでのような資本主義の理解のモデルから、全然違うスキル(能力)に来ていて、お金儲けの手段に取り込んできている。わずか10年、20年のスパンでここまで変わってきたら、50年のスパンで考えたら、全然違う社会が…。
起業家C:そもそも経済の生産性をGDPで計れなくなる。
経済学者A:幸せになったり、コミュニケーションを取れるようになるかもしれないが、GDPという旧来の市場においては計れないものが…。
起業家C:幸せって、数値化して見えてこないんですよね。経済のなかで、それがある種再生数とかPV(ページビュー、閲覧された回数)に変換されて、そこに広告が付いて、広告市場でGDPが見えてくるかもしれないが、多分数値的に可視化しきれないところが多いと思います。
経済学者A:そこで可視化しきれない時間(?)がひとりひとりの人生とか、日々の日常において大きな意味を持つのか?
社会学者D:これは、ファシズムっぽくなりません? 宗教と商品が合体して、国家社会主義的なファシズムで、すごく気持ちが悪い社会になるんじゃないか? それでいいんですか?
歴史学者B:それは、脱中心的になっていくと…。
起業家C:それは多神教で、1個ではない。
経済学者A:危険性としては、プラットホームがフェイスブックだけ、グーグルだけになったら危ういところがあるけれども、分散させていけば…。
→投稿者:「神(商品)」が多数であろうが、単数であろうが、商品を「神」と例えた以上、人間は「神」に従属する存在(転倒した存在=自ら生み出しながら、それに従属する)であり、「(神)商品」を生み出した側(資本=支配階級)による支配(抑圧)に這いつくばることである。「商品=神」こそ、商品の本質的性格を表している。
起業家C:最近、トップページがない。ユーチューブだってトップページがない。
社会学者D:確かに。
起業家C:開いた瞬間に、猫の動画がたくさん出て来るじゃないですか。
社会学者D:その人のカスタマイズ(ユーザーの好みや使い勝手に合わせて、見た目や機能、構成といった製品の仕様を変更すること)されたものが出て。
起業家C:そうです。分散的で、多神教なんです。だから、ファシズムにはならない。猫好きのコミュニティみたいなものが無数に存在していて、そのなかで経済がまわる。
社会学者D:猫好きが猫のなかで、ズーッと暮らしていくのでいいんですか?
司会者E:内向きになっちゃいますね。
起業家C:そうですね。猫好きであり、時にはアニメ好きとか、いろんなコミュニティに同時に属するような感じです。抜けたり入ったりするのは自由です。
歴史学者B:いまの話しは、新しいように見えるが、資本主義のなかの光と影、その影の部分が気になります。ぼくもわからないが、一つ考えられるのは可処分時間を奪いあう、そのなかで「マインドエコノミー」というキーワードですが、人々の気持ちを奪いあう対象にしたいとなったときに、これまでだったら6時間、7時間眠れたのが、これもしたい、あれもしたいなどと時間がどんどん奪われていって、睡眠時間が減っていくのでは?
社会学者D:睡眠時間が減りそう。
歴史学者B:睡眠時間が減っていくことに関して、睡眠時間を守ることをビジネスにすることはあり得るんですか?
経済学者A:資本主義の力でしょうか、常に、どんなものが出てきても、ガブリエルの「異なるものを内に取り込んで商品化する」という力がある。
→投稿者:新たに起きた矛盾や問題を資本の運動で解決しようとする発想の貧困さにはウンザリする。労働者人民の自己解放性への期待のかけらもない。原発建設、運転、事故処理、廃炉をビジネスにし、労働者の健康を破壊し、資本が延命(肥大)していく。資本のあくどさの典型例。
社会学者D:全部売り物(商品)になって、その(資本主義)のグロテスクさがありますね。
起業家C:誰かに労働を指示されて、いやいや労働した結果、睡眠時間が削られるのではなく、猫の動画やAKBの動画を見たくて見たくてしょうがなく、それで睡眠時間が削られているから…。
歴史学者B:見たくてしょうがないんですかね?
社会学者D:そういうふうに駆動させられているともいえる。
→投稿者:食欲、性欲、睡眠は人間の内的な欲求であり、自己回復(労働力商品としての回復)のために必要な睡眠時間を削ってでも、AKBを見たいという欲望を煽る(再生産させ)る資本(コマーシャル)の破壊性。






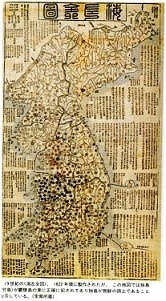




























 (2016年撮影)
(2016年撮影)
