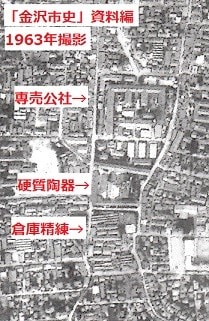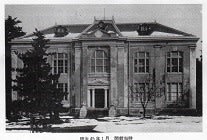二宮金次郎の亡霊 (二宮金次郎像破壊事件上申書) 柴田道子
46年前の事件
1972年「沖縄返還」の年に、沖縄出身の大城俊雄さんが名古屋から手配師にだまされて金沢に来た。11月2日、大城さんは戸板小学校の校長に「金次郎像は皇国教育のシンボルとして、こどもたちを戦争の担い手として教育した。戦後の今も、このような像が学校に建てられているのはおかしい」と説明し、持っていた大型ハンマーで粉々にしたのである。
大城さんは逮捕され、4カ月間拘留され、内灘の出島権二さんが身許引受人になり、保釈され、大城さんは私の住居に転がり込んできた。その後、金沢という地方都市の居心地がよほど悪かったのか、早々に名古屋に帰ってしまった。
この事件は大きく報道され、世論は賛否に分かれ、戸板小の金次郎像は翌1973年3月に再建されたが、2月には小将中、野町小、十一屋小、6月には中村町小、諸江小、小坂小、大野小、大徳小などの金次郎像が攻撃の対象になった。
この事件をきっかけにして、金次郎像が歴史的に果たした役割を考え、大城さんを支援する輪が広がった。児童文学者の柴田道子さんが裁判所に上申書(二宮金次郎の亡霊)を提出し、『世界』(1973年6月号)に掲載され、大城さんの事件は全国版になった。
柴田道子さんは1975年8月14日に亡くなったが、私は金沢刑務所の独房で知らされ、41才というあまりに若い死に絶句した。いずれも半世紀前のことだが、その間に教育基本法が改悪され、道徳教育がはじまり、教科書8社の小学校5、6年生の道徳教科書には金次郎が出ている。いま、金次郎像とは何かを改めて確認する必要があり、柴田道子さんの上申書(二宮金次郎の亡霊)を投稿する。
二宮金次郎像破壊事件 上申書 柴田道子
裁判長さま
昨年11月2日、この日も暮れようとしている頃、一人の男の人が金沢市立戸板小学校玄関横にある、陶器製の二宮金次郎像を壊しました。「子どもの役にたたない……」といって、ハンマーで粉々にしたこの男の人は、沖縄県出身の大城俊雄さんでした。私は大城さんご自身のことを、あまり多く存じあげません。ただ彼が50歳の男でも、20歳の青年でもなく、37歳であるということだけで、私は深い感慨にふけるのであります。「子どもの役にたたない」という彼の叫びとその行為は、私に大きな衝撃をあたえました。大城さんが37歳というお年でなかったならば、おそらく遠い北国で起こったこの事件は、日常のせわしさのなかで、私の記憶のひだに留まることがなかったでしょう。
その衝撃は、すぎ去った日に打ち砕き葬り去ったはずの亡霊に、再び出あったという驚きであります。かつての亡霊が、生き生きと甦っているのでした。私はこの亡霊について、あなたさまにご報告する義務と責任を、痛く感じている者でございます。失礼とは存じますが、生まれてはじめてこのような上申書というものを書かせていただいております。
頼もしい皇国少女
私は昭和9年3月に、現在の東京都北馬込に生まれました。大城さんより3年上にあたりますが、学年は私の方が2つ上です。15年戦争の真最中に生まれました。太平洋戦争は私の小学校1年の3月から、6年の8月までにあたります。つまり私は母親の腹の中にいる時から、軍国主義思想のもとで、軍国主義教育を受けて、成長しました。頼もしい皇国少女であった私は、敗戦という体験がなかったならば、今頃は優秀なファシスト小母さんになっていたところでした。
いわゆる戦中派と呼ばれます、私たちの兄の世代の人々は、世の中には色々な考え方や思想があることを学んでおります。彼らは私たちよりもはるかに「自由」という意味を知っておりました。ところが私たちは、生まれてきた時は、世の中はすでにひとつの価値観でぬりつぶされ、組み変えられておりました。ご存知のとおり軍国主義のもとでは、皇国精神と絶対主義思想のみであります。私たちは皇国少年、少女と呼ばれ「非常時」に成長いたしました。
絶対主義思想を骨のずいまでたたき込まれたのではなく、そうした思想によって骨肉を作ってきたのです。私たちのなかに流れる血はファシズムそのものでした。直接的にあった権威は、教師と父母であります。その権威は天皇に通じており、私たちを圧制していたのです。もちろん子どもである私たちは、圧制という自覚はなく、真から信じておりました。
家訓としての「二宮翁夜話」
私の父は静岡県榛原郡の出身です。農家の四男であります。父の叔父にあたる人が、同じ榛原郡の吉田で報徳社をたて、弟子を集めて熱心に布教をしておりました。祖父は資力がなくて、長男にしか学問をさせませんでしたから、向学心に燃えていた四男の父は、足しげく青田の叔父のもとに出入りしていたようです。貧農から身を興し「勤・倹・譲」をもって財を得、幕府の役人にまで上昇した二宮尊徳は、父には最高の師であったに違いありません。
祖父は子どもたちの中では頭のよい父を、金のかからぬ教員養成所へ入れました。父は養成所へ通うかたわらも、叔父の家に出入りしました。丁度養成所へ通う道すがらに、叔父の家はありました。父がどの程度尊徳の教えを、自らのものにしていたかわかりません。しかし私の察する以上に、尊徳に傾倒していたことは事実であります。それは父のその後の人生にあらわれておりますから。
父は教員養成所ではものたりなく、やがて上京し、書生をしながら高等教育を受けました。祖父からの援助はあるはずもなく、豆腐を常食として学校に通ったということを、幼少の私はよく父から聞かされております。今日では豆腐は、肉の一枚にあたる高値でありますが、当時は最も安い部類の食品であったようです。月謝が支払えない父は、特待生の恩恵にあずかるべく、終始一番で学校を卒業しております。こうしたことは父の自慢話に聞いたものです。父の生き方、父の子どもに対する教育は、二宮尊徳を離れて考えられません。幼少から私たち兄妹は、毎朝神棚と先祖(仏壇)に手をあわせ、床の間にかけてあった掛け軸の文字を、読まされてからでないと、朝食にあずかれませんでした。私は字が読めない頃から、大きい兄たちと並ばされて、この掛け軸を読んでおります。掛け軸の文字は漢文であり、この意味などわかろうはずがありません。実はその掛け軸は「報徳訓」でした。私は何やら意味のわからぬまま、この報徳訓を暗話しております。
「ホウトククン フボノコンゲンハ テンチノレイメイニアリ……」
「二宮翁夜話」をご家訓として育った私は、生まれてはじめて学校の門をくぐった時、そこに二宮金次郎の銅像があったことに、何の不思議もありませんでした。それどころか大変親しい師が、銅像になっているのだなあと思ったほどです。少年二宮金次郎は、質素・倹約・勤勉、父母に孝に兄弟に友にのお手本でありました。
奉安殿と金次郎像
金次郎の銅像は、奉安殿と共に小学校時代の私たちに君臨しておりました。天皇・皇后の「御真影」が祭られていた奉安殿は、校庭の正門横の塚にあり、金次郎像は東門横のジャングルジムと並んでありました。当時は一棟しかなかった馬込第三小学校の校舎の、どの教室からもこの2つのシソボルは見えました。支配する者と、支配される者としての2つの精神的象徴は、具体的な形をもって、私たち子どもを圧倒しておりました。登校下校の時私たちは、奉安殿に最敬礼させられております。させられたというのではありません、ごく自然にそうしたのです。生徒が宿題を忘れたり、規律を破ると、教師は薪を背おわせて金次郎像の前に立たせます。薪でなく水の入ったバケツという時もありました。そして何と守らなければならない、多くの規則や規律があったことでしょう。金次郎像は、親しく幼年時代の私たちの血肉を作りました。幼年時代の体験が、どんなにかその人問のその後の人生を支配するか、影響をおよぼすかは、心理学者や精神医学者の言を待ちません。
柴刈り縄ない/わらじを作り/親の手助け/弟を世話し/兄弟仲よく/孝行つくせ/手本は二宮金次郎
今から思えば、決して詩的でないこの小学校唱歌を、私たちはうたいながら成長しました。国定教科書に登場するだけではなく、唱歌にまで金次郎が登場したというこの事実は、重大な意味を持っております。金次郎は、皇民化教育の、最も具体的で親しい先生となっていたからです。この土の思想家は、何よりも経済主義者であり実践論者であったことが、民衆の心をつかんだのでありましょう。第1期国定教科書令が公布されましたのは、1903年(明治36年)の4月です。この時から敗戦まで長い間金次郎は、日本の民衆の脳裏に、幼くして先生として焼きつけられました。
平民から出た偉人の役割
奈良本辰也『二宮尊徳』(岩波新書)は次のように申しております。「井上哲次郎は、国定教科書のなかに二宮尊徳が入れられたことについて次のようにいっている。『国定教科書に二宮翁を加へたるは、最も選の宜しきを待たるものと謂ふ可し。我国史中模範人物としては中江藤樹あり、貝原益軒あり、上杉鷹山あり、水戸の義公あり、烈公あり。共に是れ大和民族の精粋にして、後世の模範となすに足るべきものに相違なきも、鷹山、義公、烈公の如きは、何分大名なるが故に、一般平民に其縁頗る遠く、感化又或は及び難きものあり。独り二宮翁は然らず、翁は平民にして、而も農夫の子として成長せり。故に農家の子女には、其境遇近く、其境涯相似たり。境遇等しきが故に、教師は学びて怠らず、勉めて休まずんば、農家の子女も、亦能二宮翁の如くなり得べしとの希望を抱かしむるに足る』(井上哲次郎「学説上における二宮尊徳」留岡幸助編『二宮翁と諸家』所収)というのである。しかしこれをつぎの言葉と対照するとまことに面白い。それは、やはり同人の言葉であるが『余は一たび国定教科書中に吉田松陰を加へんと欲せしも或人之に反対して日く、精神は兎も角も、彼は時の政府に反対したるもの、小学生徒には終に不適当の人物たるを免れずと。是に於てか遂に松陰を加へざる事となれり。』(同上)まことに意味の深い選択であったといえよう。ここに、政府が尊徳を重んずる理由は顕然たるものがある。このようにして、身長6尺、体重25貫、激せば大藩の重臣をも小児の如くしかりつけて後にひかない、そうした男が、いつまでも16歳のかよわい少年の姿でとらえられ、勤・倹のみが彼を現わす代名詞のようにもなり、あの校庭に立った二宮金次郎の像が彼のすべてを象徴するようになったのであった。」
金次郎がどのような意味を持って、国民を導く立場にむかえられたか、教科書の編者自身がせきららに語っているではありませんか。太平洋戦争が激化し、菓子屋の店先きには「ほしがりません勝つまでは」という紙がはり出されました。子どもたちの生活までも根こそぎ「鬼畜米英」にむけられたのであります。そうしたなかで、私たちの先生二宮金次郎像は、プロソズであったために弁当箱やなべかまと一緒に、お国のために「出征」していきました。金次郎は大砲の弾になったのです。像になった金次郎も、実によい皇民であったわけです。長刀や竹槍をふりまわす私たち児童を見守る金次郎は、ブロンズから石像にかわりました。お国のために「銃後」を守っていた私たちは、東京空襲がはじまると、学童集団疎開をしました。
学童疎開と隆君の死
次の世を背おふべき身ぞたくましく、正しくのびよ里に移りて
皇后陛下の「聖歌」に送られて、私は5年生の春から6年生の秋まで静岡県の伊豆へ、そしてここでも空襲にあい、富山県の西礪波へ再疎開しました。敗戦は西礪波の寺でむかえております。子どもにとっての戦争とは何であったかは、私の学童疎開体験が如実に語ってくれますが、今はくわしくお伝えする余裕がございません。
疎開中、最高学年になった私は、教師の指導のもとに、下級生を統率してきました。当時教師の権威は絶対的でありました。日常生活の中で、金次郎の教えよろしく、教師の手を助け、弟や妹たちをよく世話しました。石ころがじゃがいもにみえ、ワカモト(薬)を空腹のためにたべてしまうような、食糧難でした。敗戦の年の夏、私たちが手あつく看護した3年生の隆君は、栄養失調と小児結核で疎開先きで死亡しました。寮母先生と交替で隆君を背おい、私は往復5キロの道を、寺から町の医者まで通いました。彼は次第にやせ細り、ミイラのようになって死んだのです。
「おかあさんにあいたい」と隆君は虫の息で私に申しました。生きていた隆君のぬくもりと、彼の最後の言葉「ありがとう」を、私は忘れません。
私は太平洋戦争で、肉親の一人を失っておりますが、隆君の死はその時受けた悲しみ以上のものでした。小さい生命に襲いかかる死への憎しみは、悲しみをとおりこした怒りとなって、その後の私の中に生きております。当時の私たちに「東京に帰りたい」「おかあさんにあいたい」という言葉は禁句でした。皇国少年、少女たちはよくこの規律を守ったのです。隆君のこの世での最後の言葉が、この禁句であったことが、私の心を大層しめつけました。
直接的には飢えが、大局的には戦局の深刻さが、私たちの心情を左右しておりました。隆君の死は、私たちに大きな翳りを落しました。次は自分の番ではないかということです。喜びや苦しさやひもじさを、共にしていた私たちです。隆君の死を、自分の一部の死と思いました。彼の死は敗戦直後のことでありましたが、権威に対する不信は、敗戦を待たずして子どもたちの中に不安となって、芽ばえてきていたのです。
隆君のおとうさんが、角の焼けこげた皮のトラソクを持って、息子の遺骨をむかえにきた時、私たち学童はどうしても隆君の骨を渡さないといって、はじめて教師に刃向かいました。子どもたちは友の骨をかかえて、布団部屋に龍城したのです。私たちは彼の骨をまじえて、誓いあいました。隆君と一緒に生きるのだ、隆君が東京に帰る時は、私たちも帰る時だと。生きたい生きたいと、必死で死と闘いながら死んでいった友の、奪い去られた生命のぶんを、私たちが生きぬくのだと誓いあったのです。
児童文学の道へ
少女時代の戦争体験が、私を児童文学の道に歩ませました。私はどんなに年をとっても、生きているかぎり子どもの側に身をおき子どもらの実存を、表現していきたいと思いました。それは子どもにとっての太平洋戦争とは何であったかに、はじまっております。子どもも一個の個性を持った人間存在です。彼らにとって、この世はどんな風に存在しているのでしょうか。子どもたちも社会に対して、子どもとしての希望を持ち、反発を持ち、あるいは喜びを持っているはずです。私はそれを表現していこうと思っております。このことが沢山の思いを残して、幼くして死んでいった隆君の心を生きることであると思いました。子どもは社会の仕組の中で、疏外されています。そして子どもは、大人たちに対して自己を防御しにくい存在でもあります。
奪われた教育権
大城俊雄さんは、隆君と同じ学年であります。彼は敗戦の年3年生であったと申しております。大城さんが幼年期にどのような教育を受けたか、それは私の経験と似ているのではないでしょうか。しかしさらに彼は、沖縄からの出かせぎの父母を持ち、差別と貧困の日常を強いられております。君に忠、親に孝、質素、倹約の二宮先生は、私たち以上に大城さんの幼い心をとらえたことは、信じるに疑いありません。同じ世代で同じような体験を持つ私は、彼の思いが体中で感じられます。
大城さんが「こんなもの子どもの役にたたん」といって金次郎像をたたき壊す時、彼は幼年時代の己の体に、ハンマーを打ちおろしているのであります。そして何よりも重大なことは、彼が戦争中の教育しか受けていないという事実でありましょう。大城さんは、3年生までしか学校に出ておりません。9歳にして公教育からほうり出されているのです。沖縄出身者の家庭に強いられている資質と差別を、想像しないわけにはいきません。沖縄出身者にむけられる巷に生きている迫害は、ぬくぬくと教育を受けてきた私たちには、想像を絶するものがありましょう。
戦後民主主義教育、あるいは義務教育は、彼のような子どもたちを見捨てていたところに、なりたっていたことを痛く反省させられます。大城さんは教育を受ける権利を、完全に剥奪されてきたのであります。このことへの反省なくして、彼の行為を論ずることはできません。子どもは社会に対して、両親に対して、自己を防御しにくい存在であることを、差別を身をもって体験してこられた大城さんは、よく理解しておりました。彼は手紙の中で次のように書いております。
「現在の社会組織にも絶望を覚えます。金次郎のように何んでもかんでも勉強して最高学府の教育を受けねば人間らしい豊かな生活に達せず天皇や支配者の、屍生贅にされる弱肉強食の組織にかぎりない悲しみといかり絶望を覚えます。ですから児童さんが<教育ママ>に虐待されているのです。」
「こんなものは役にたたん」
子どもが教育ママに虐待されているという、現実の子どもたちの声をまっすぐ聞きいれ、大城さんはこれを指摘しております。
敗戦は子どもたちに、何を教えたかと申しますと、大城さんのいう「こんなものは役にたたない」ということでした。母親の腹の中にいる時から、すなわち骨のずいから皇国思想で人間形成された私たちです。敗戦はこの肉をこの血を否定することでありました。大人たちのように、頭の切りかえができる軸など持たされておりませんでしたから。戦争下に自己形成をはじめていた私は、宇宙を支配していたこれまでの権威の崩壊を、目の当たりに見て、これまでの自己を全く否定することを迫られました。信ずるものは、自分以外になく、これから自分が創造していく以外にないということです。私たち疎開児童は、帰京すると二宮金次郎の石像を、自分たちの手で泣きながらこなごなに壊したのでした。この行為は、自分自身を鞭打つ行為だったのです。私は今、大城さんの行為に、27年前の私たちの姿を見たのでした。
実際教師たちは、これまでの日本の行為は植民地戦争であり侵略戦争であったと、否定すべきものであると私たちに教えました。民主主義というのは、みんなが参加してみんなで創造していくのだと、私たちほ学びました。民主主義は上から降ってこないということです。下から生まれてくるものであると。大城さんは9歳で学校を追われ、いわゆる戦後教育を受けておりません。このことは重要なことです。その後今日まで大城さんは、さまざまに迷いながら戦後を、孤独のうちに模索してきました。この間彼はどのような待遇で、どのような仕事にたずさわり、生活を維持してこられたでしょうか。このことも私はくわしくは存じません。
大城さん一家の苦難
大城さんのおかあさんは、若くして本土に渡り、紡績女工をして働いております。その後沖縄に帰って、おとうさんと結婚されました。やがて大城さんは3人兄弟の次男として、沖縄で生まれております。一家は職を求めて昭和16年本土に渡り、おとうさんは和歌山県で温泉の釜たきをはじめました。戦況の悪化と、戦時下経済は、釜たきの職をおとうさんから奪い、名古屋の焼け跡に出て、廃墟で養豚業をはじめたということです。生活が苦しく敗戦を迎えると、おかあさんは沖縄の実家へ戻りました。大城さんは貧困のなかで母に去られ、小学校は事実上3年で中退したと申しております。その後は長欠児童であり、やがて学籍簿すらも消されてしまうのです。
幼い大城さんが食べるために、倒れずに生きるために、どのようにさすらってきたか、彼は「私は業を背負って生きているようなものです」「私の歩んできた道は、到底人に理解してもらえないかもしれない」と手紙で書いております。戦時下の本土と沖縄の混乱の中で、大城さん兄弟は籍を入れられずにすぎ、やがて敗戦とそれにつぐ沖縄の分離下で、彼らは戸籍がないという状況のまま、今日をむかえております。おとうさん勇一氏の出身は、沖組県国頭郡今帰大字親泊であります。おかあさんマツさんは、幼い日の記憶をたどるとグシケンという所で、おかあさんの兄妹はグシケンでキイガヤ商店なる商いをしているということです。大城さんは、本籍はないが「わんやまくとぬうちなわんちゅうです=私は誠の沖組県人」と申しておられます。
戸籍がないので、パスポートがおりず、大城さんは故郷に帰りたくとも帰ることができませんでした。そして再会できぬまま昨年おかあさんを亡くしております。私は「おかあさんにあいたい」といって死んでいった隆君を、大城さんに見ました。彼は戸籍がないので、本工員として勤めることもできず、臨時工に甘んじなければなりませんでした。港湾、土木建設の労務者として、西に東に放浪しております。大城さんの個人生活は、戦後を迎えておりません。大城さんが「こんなものは子どもたちの役にたたない」といって金次郎像を打ち壊す時、彼は自らの手で戦後を創造しようとしているといえましょう。
低賃金で転々と渡り歩く大城さんの不幸は、私たちの歴史が沖縄県民に強いた、迫害の歴史でもあります。彼はあまりにもひどい待遇で今辞めてきた職場を後に、明日の職をどこに求めていくか考えながら、ふと足を戸板小学校にむけました。正面玄関横に、大城さんは彼の不幸を形成した二宮金次郎の亡霊を見たのです。この時大城さんは一瞬にして、幼少期を思いおこしたことでしょう。一瞬にして戦後28年の地獄をはうような、生活を思いおこしたことでしょう。大城さんが金次郎像を壊す時、子ども時代に犠牲しか払わなかった戦争責任を追及しているのです。当時は私たちは被害者でした。しかし現在は歴史に、社会に責任を持っております。
事件の動機
大城さんは手紙で、事件の動機を次のように申しております。「事件の当日は紅葉の秋です。もみじのような可愛らしき手をした幼なき子供さんに、大なる夢を託し重き荷を背負わせるのは、信仰上又は道徳上許しがたき義憤を覚えた訳に、存じますが―」「私は我が身をかえり見て学校当局に望みますのは過去のような矛盾した教育ではなく勝手に大人の考え方を幼い心に吹きこみ重荷を背負せないで子供は平和に生きる道を自らの手でえらび平和を求め行く権利をおてびきして下さるよう学校当局に望みます。ですから<道具衆>としてかつぎだされた<金次郎像>が今日もなお校庭に放置されて居るのは矛盾してふさわしく思えません。第二次大戦では大人の争いや戦いに子供をまきこんだり戦いの道づれにしたのですからその死を悼み永遠にざんげする意味にても<二宮像>を撤去してそれぞれの学校当局の児童犠牲者を校庭に建立したほうが真の平和を求める姿ではなかろうかと考えます。ちなみに小豆島の<二十四の瞳像><沖縄の健児の塔><ひめゆりの塔>などが大人の争や戦いに子供をまきこんだ責任を感じさせ戦争防止に役立のではなかろうかと考えてのこのたびの事件で御座居ます。」
そして大城さんは、親戚のおばあさん一家に想いをはせておりました。「近卑な一例を取りましても沖縄に住居する私の親戚のおばあさん一家は5人の男子の子宝に恵まれ乍ら第2次大戦で鉄の規律で5人の息子を奪われ、戦いにかりだされ、壮烈戦死の犠牲を被ており、そして何んの報くわれることも、戦争責任者である天皇を遺恨と憎しみの中に死んだとの風の便りです。」
沖縄の子どもたち
私の学童疎開中の日記(1945年7月1日)には「きょう寮長先生のごくんわに、沖なわの赤国民学校の生徒ぜんいんが、手りゆうだんをもって、敵じんにのりこんでいったと、しんぶんにはうどうされたことをおっしゃいました。私は沖なわの生徒はりっばだと思いました。私はなみだがでてきました。私もがんばりたいといっしょうけんめいに思いました」と書いてあります。
今次大戦の沖縄決戦で、沖縄の子どもたちがどのような運命と犠牲を強いられたか、これまた本土の子どもとは比較にならないものがあります。私は大城さんが沖絶県出身であることに、深い痛みと反省を覚えます。彼の行為は私への、とりわけ子どもの文学にたずさわる者にむけられた糾弾として、受けとめております。
言語道断の行為
本件の告訴人は、岡良一氏名義の金沢市長になっております。告訴状は次のようなものでした。「昭和47年3月2日午後4時20分ごろ、金沢市立戸坂小学校前庭において二宮尊徳(陶製)を理由もなく乱打破壊したことは言語道断の行為であり、尊敬する立像を失った児童の精神的影響は極めて大であるため、調査のうえ処罰願います。」
大城さんが金次郎像を乱打破壊したことは事実であり、彼もこれを認めております。彼の行為には深い動機と理由があったことを、私はこれまでに申し上げてきました。被告人にとっては、表現不可能なほどの、いいつくせぬ理由がありました。しかし私たちの生活する法社会では、破壊行為は非難されるものとなっております。百歩ゆずってそれを受け入れても、被壊せざるを得ない歴史的背景を考えますと、どちらが重たいものでしょうか。答えは明白だと思います。取りかえしのつかない無惨な犠牲のうえに得た28年前の尊い教訓を、被告人は破壊という行為において、金次郎像が象徴している思想にむけたのです。
子どもたちに死の犠牲を強い、子どもたちにとって侵略戦争のシンボルでありました二宮金次郎像が、市内の小学校校庭にあること自体が、反省されるべきことと思います。戦中からひきつづき建ちつづける金次郎像を擁護することは、赤国民学校児童や無数の隆君の死を歓迎することであります。侵略戦争を掩護することであります。
奴隷の思想
もともと二宮尊徳の思想は、金次郎に象徴されるもののみではなかったでしょう。しかし問題は、尊徳という経験主義者は、天下国家の大勢も運命も考えなかったことにあります。彼には政治批判がまったくありません。そのことが国民学校児童や、無数の隆君の死を歓迎することになったのです。二宮のいう勤勉と従順は、奴隷の思想でありましょう。権力を持つ者には、都合のよいことに違いありません。尊徳は「貧にして富之非を見出し喧譏するものは不仁なり」(『農家大道鏡』)と書いております。農民一揆は、農民の方に責任があるということのようです。また尊徳は「知足安分」といって、百姓は百姓、工人は工人として分に応じた生活をせよと申しております。身分制度という階級制度を擁護しているのです。時代が時代だったからという理解の仕方はありますが、それと評価とは別の次元で語られなければならないでしょう。ところが尊徳自身は、努力に努力を重ね、農を脱出して士になっております。身分制度の厳しい徳川時代に、これは全く信じられないようなことですが、そこにはこれまた信じられないような力行がありました。
告訴状は「言語道断の行為」と、確信を持って申され、「尊敬する立像を失った児童の精神的影響は極めて大である」と述べております。果たして金次郎像が、今日の子どもたちの尊敬の立像となっておりますでしょうか。もしそうだとすると、それは恐しいことです。何故なら「いつかきた道」ですから。
敗戦直後GHQでは、「教育上よろしくない」という意向で、金次郎像を取り払うようアドバイスをしております。GHQの教育担当者が、各県に出むいて指導をしておりますが、地城によりまた担当者の姿勢により、まちまちであったようです。取り払われなかった地方もかなりありました。東京では徹底的に取り払われ、民主化の模範を示したということです。
子どもたちの受けとめ
現実に今日の子どもたちが、金次郎像を尊敬しているかどうかと申しますと、はっきり言って尊敬もしておりませんし、関心も持っておりません。芸術作品としても美的とはいえないこの像に、関心を持つ子どもは、次のように評価しています。
「この子、交通事故を起こすよ、あぶないよ。この子、目が悪くなるよ。」などであります。この意見が金次郎像からうける、子どもたちの偽りのない言葉です。子どもたちは今のところ金次郎像の持つ思想を、現代的には非合理なものとしてしか、受けとめておりません。しかしそれはあくまでも今のところであります。支配者が意識的に都合のよい金次郎の思想を、子どもたちへ吹き込むことは可能です。そしてこれまで金次郎が登場する場面は、必ず社会不安や内外の情勢の厳しい時でありました。国民に不平をいわさず、しっかりおさえておく必要のある時でした。
教育勅語と道徳教育
すでにふれましたが、国定教科書令が公布されたのは、1903年であります。この年から画一化された教科書が、全国で使用されるようになりました。金次郎はここにおいて、全国のどのような辺地の子どもたちの前にも、登場するのであります。(1900年、義務教育4年制、1907年、義務教育6年制となる)ところが、これより先き1886年(明治19年)に臨時修史局が設置され、教科書検定条令が公布されました。明治19年に、国定教科書が始まったとみていいでしょう。先きに述べました井上哲次郎の頭の中には、この時金次郎がのぼっておりました。そして明治政府は、1889年(明治22年)に従4位の位を、尊徳に贈っております。彼はここで明治維新に功労のあった元勲たちと肩を並べるのでした。何て意図的なことでしょう。
明治22年という年は、大日本帝国憲法が発布され、その翌年には教育勅語が発布されました。立憲政治は、権利に目覚めた「市民」をいやおうなくつくりだします。為政者はそれに呼応して「臣民」としての心構えを明らかにしておく必要がありました。教育勅語は、権力操作のために、天皇親政の徹底化としてでてきました。教育勅語こそ、道徳教育の基本でありましょう。
二宮金次郎が教科書に登場したのと、二宮尊徳が政治上のテコとして、積極的に支配者に利用されはじめたのは、軌を一にしております。1905年11月、日露戦争の直後、二宮尊徳50年祭が、政府の手で行われました。この50年祭を機縁として、内務省、農商務省の官僚が中心となり「報徳会」を結成しました。「報徳会」は政府の地方改良運動の理念的範型となったものでした。報徳会運動は、日露戦争後の社会不安と、内外の情勢の緊迫化の中で進められました。『日本の百年』7巻「明治の栄光」(筑摩書房)によりますと、報徳会結成に参加した顔ぶれを、次のように伝えています。
「内務・農商務官僚のほか、地主、篤農家、郡長、村長、村役場書記、師範学校、小学校長、僧侶、産業組合役員、銀行、会社重役等々いわば日本社会の底辺を支える地方指導者を網羅していた。山路愛山が<日本帝国の4本柱>と呼んだ村役人、学校の先生、寺の坊主、駐在所の巡査のうち、巡査をのぞいた各層の代表者が集まり、その周辺に桑田熊蔵、神戸正雄、内田銀蔵らの学者達も動員されるというかたちをとった。」
さらに同書は、「報徳会は、尊徳の遺訓とされた4原則―至誠・勤勉・分度・推譲の徳目にもとづいて、社会調和をはかろうとする官民有志の組織であった。その場合、会の主体となるのは地方名望家であり、彼らの指導性を再編することによって、予想される階級対立の激化、社会問題の蔓延を阻止しょうとするものであった。そのため内務官僚たちは、地方名望家層の実情を正確に把捉しょうとつとめた。」といっております。報徳社のねらいは、さらに次のようなところにもありました。
「従来のように郡役所の若い役人が地方の名望家である村長を監督するのではなく、自治を奨励しながら教えを導いてゆく、すなわち指導するということにあった。」(石田雄『明治政治思想史研究』の聞き書き)
国づくり、人づくりの手本
日露戦争後の社会矛盾を克服するために、内務官僚によって推進されました新しい国づくり、人づくりの手本として、二宮尊徳の思想は恰好でありました。民衆は支配者に逆らわず分をわきまえ、農村の矛盾(疲弊)をひたすら努力によって、すなわち勤勉と倹約で解決していくよう導かれたのです。二宮尊徳の「勤・倹・譲」は道徳的な経済生活であります。勤は勤勉であり、一生懸命働くことでした。倹は倹約をすること、譲とは推譲のことで譲道があってはじめて人間の社会がなりたっているとしました。尊徳は申しております。「親にも朋友にも譲らずばあるべからず、村里にも譲らずばあるべからず、国家にも譲らずばあるべからず。」(「夜話」)
ところで尊徳の譲とは、藩を建てなおし、幕府の困窮を救うものとしてありました。そして確かに彼は、その力を発揮しております。彼は貧しい人びとにも、しばしば救いの手をさしのべておりますが、それは彼らを「勤」に奮起させるための奨励金としてです。貧窮の根元である矛盾を正さずに、それをとりつくろうことに全力が傾けられるのでした。
明治の天皇制国家が、彼をして民衆の心をとらえようとした意図を、察することができます。赤貧洗うがごとき貧乏から、努力に努力を重ねて、国のためにつくしたという二宮先生は、貧しい民衆のアイドルになりました。貧乏でも高い地位や名誉がなくとも、十分お国のためになれると、民衆を導くことは、為政者にとって結構なことに違いありません。くりかえしますが、義務教育下の国定教科書によって二宮先生の教えは、全国津々浦々の子どもたちの脳裏にやきつきました。そしてまた実生活では、報徳会が全国的に活躍しております。
二宮金次郎の亡霊
こうした歴史経過を考えあわせますと、これまで放置されておりました金次郎像が、法廷にまで引っはり出されて来たこと自体に、ただならぬ不安を感じるのであります。教科書の反動化が法廷で論じられ、争われている今日、子どもの側に身をおくことに自己を律し、子どもの文化創造を仕事にしている私たちにとって、金次郎像をめぐる今回の事件に、ロをつぐんでいるわけにはいきませんでした。
アメリカ経済の危機の現われであるドルの低落は、国際資本の圧力を円にもたらしています。経済のことはよく理解できませんが、円の変動相場制は、日本経済の虚弱体質の破れ目ではないでしょうか。消費文化の見せかけだけの繁栄は、目の前に大きな動揺が待っていることを、私たちにひしひしと感じさせます。二宮金次郎の「勤・倹・譲」が動員される危惧をいだくのは、ひとり私だけではないと思います。
「交通事故にあわない、目が悪くならない」時代にかなった金次郎が、現われてこないともかぎりません。経済状況の行きづまり、インフレによる物価高、子殺しをする親が次々と現われ、公害に対する市民の怒りが結集しております社会情勢であります。
器物損壊という罪名で、4カ月近くも大城さんの身柄を拘束し、なおかつ50万円の保釈金ということに、私は驚きをかくせません。建立当時(昭和初期)、金次郎像は5円か10円であったそうであります。戸板小学校長が、教育委員会に提出した報告書には「時価1万3000円」とあり、検察官の起訴状には「時価10万円」となっております。検察官にはインフレを促進している傾向がみられます。検察官はもしや二宮金次郎像に、精神的思想的「高価」を計算しているのではないでしょうか。ここに二宮金次郎の亡霊が、大手をふって生きていることがわかります。
今回の大城さんの行為によって、私は太平洋戦争で死んでいった子どもたち、とりわけ私の記憶のひだにたたまれた隆君や、沖縄の赤国民学校の児童たちのことを思いおこし、胸をかきむしられております。
世界の良心と民主主義
裁判長さま、私はあなたの真理にかなった民主的なお裁きを、二宮金次郎によって自己を形成し、且つ死んでいった無数の子どもたちと共に見守りたいと思います。かつて東京裁判の際、キーナン検事は「原告は世界の良心と民主主義である」と申されました。本件の告訴者は、金沢市長でありますが、お裁きになりますあなたさまは「世界の良心と民主主義」をもって、お裁き下さいますよう、あえてお願い申しあげます。
以上
注:小見出しは当会が付けた。漢数字はアラビア数字に、誤字は補正し、引用文の改行も適宜おこない、読みやすくした。大城俊雄さんに関する原資料を保管していたのだが、長い年月の過程ですべて失ってしまった。金次郎像破壊事件は柴田道子さんの上申書と渡久地政司さんのHP(富村順一さんら救援活動)に依るしかない。
46年前の事件
1972年「沖縄返還」の年に、沖縄出身の大城俊雄さんが名古屋から手配師にだまされて金沢に来た。11月2日、大城さんは戸板小学校の校長に「金次郎像は皇国教育のシンボルとして、こどもたちを戦争の担い手として教育した。戦後の今も、このような像が学校に建てられているのはおかしい」と説明し、持っていた大型ハンマーで粉々にしたのである。
大城さんは逮捕され、4カ月間拘留され、内灘の出島権二さんが身許引受人になり、保釈され、大城さんは私の住居に転がり込んできた。その後、金沢という地方都市の居心地がよほど悪かったのか、早々に名古屋に帰ってしまった。
この事件は大きく報道され、世論は賛否に分かれ、戸板小の金次郎像は翌1973年3月に再建されたが、2月には小将中、野町小、十一屋小、6月には中村町小、諸江小、小坂小、大野小、大徳小などの金次郎像が攻撃の対象になった。
この事件をきっかけにして、金次郎像が歴史的に果たした役割を考え、大城さんを支援する輪が広がった。児童文学者の柴田道子さんが裁判所に上申書(二宮金次郎の亡霊)を提出し、『世界』(1973年6月号)に掲載され、大城さんの事件は全国版になった。
柴田道子さんは1975年8月14日に亡くなったが、私は金沢刑務所の独房で知らされ、41才というあまりに若い死に絶句した。いずれも半世紀前のことだが、その間に教育基本法が改悪され、道徳教育がはじまり、教科書8社の小学校5、6年生の道徳教科書には金次郎が出ている。いま、金次郎像とは何かを改めて確認する必要があり、柴田道子さんの上申書(二宮金次郎の亡霊)を投稿する。
二宮金次郎像破壊事件 上申書 柴田道子
裁判長さま
昨年11月2日、この日も暮れようとしている頃、一人の男の人が金沢市立戸板小学校玄関横にある、陶器製の二宮金次郎像を壊しました。「子どもの役にたたない……」といって、ハンマーで粉々にしたこの男の人は、沖縄県出身の大城俊雄さんでした。私は大城さんご自身のことを、あまり多く存じあげません。ただ彼が50歳の男でも、20歳の青年でもなく、37歳であるということだけで、私は深い感慨にふけるのであります。「子どもの役にたたない」という彼の叫びとその行為は、私に大きな衝撃をあたえました。大城さんが37歳というお年でなかったならば、おそらく遠い北国で起こったこの事件は、日常のせわしさのなかで、私の記憶のひだに留まることがなかったでしょう。
その衝撃は、すぎ去った日に打ち砕き葬り去ったはずの亡霊に、再び出あったという驚きであります。かつての亡霊が、生き生きと甦っているのでした。私はこの亡霊について、あなたさまにご報告する義務と責任を、痛く感じている者でございます。失礼とは存じますが、生まれてはじめてこのような上申書というものを書かせていただいております。
頼もしい皇国少女
私は昭和9年3月に、現在の東京都北馬込に生まれました。大城さんより3年上にあたりますが、学年は私の方が2つ上です。15年戦争の真最中に生まれました。太平洋戦争は私の小学校1年の3月から、6年の8月までにあたります。つまり私は母親の腹の中にいる時から、軍国主義思想のもとで、軍国主義教育を受けて、成長しました。頼もしい皇国少女であった私は、敗戦という体験がなかったならば、今頃は優秀なファシスト小母さんになっていたところでした。
いわゆる戦中派と呼ばれます、私たちの兄の世代の人々は、世の中には色々な考え方や思想があることを学んでおります。彼らは私たちよりもはるかに「自由」という意味を知っておりました。ところが私たちは、生まれてきた時は、世の中はすでにひとつの価値観でぬりつぶされ、組み変えられておりました。ご存知のとおり軍国主義のもとでは、皇国精神と絶対主義思想のみであります。私たちは皇国少年、少女と呼ばれ「非常時」に成長いたしました。
絶対主義思想を骨のずいまでたたき込まれたのではなく、そうした思想によって骨肉を作ってきたのです。私たちのなかに流れる血はファシズムそのものでした。直接的にあった権威は、教師と父母であります。その権威は天皇に通じており、私たちを圧制していたのです。もちろん子どもである私たちは、圧制という自覚はなく、真から信じておりました。
家訓としての「二宮翁夜話」
私の父は静岡県榛原郡の出身です。農家の四男であります。父の叔父にあたる人が、同じ榛原郡の吉田で報徳社をたて、弟子を集めて熱心に布教をしておりました。祖父は資力がなくて、長男にしか学問をさせませんでしたから、向学心に燃えていた四男の父は、足しげく青田の叔父のもとに出入りしていたようです。貧農から身を興し「勤・倹・譲」をもって財を得、幕府の役人にまで上昇した二宮尊徳は、父には最高の師であったに違いありません。
祖父は子どもたちの中では頭のよい父を、金のかからぬ教員養成所へ入れました。父は養成所へ通うかたわらも、叔父の家に出入りしました。丁度養成所へ通う道すがらに、叔父の家はありました。父がどの程度尊徳の教えを、自らのものにしていたかわかりません。しかし私の察する以上に、尊徳に傾倒していたことは事実であります。それは父のその後の人生にあらわれておりますから。
父は教員養成所ではものたりなく、やがて上京し、書生をしながら高等教育を受けました。祖父からの援助はあるはずもなく、豆腐を常食として学校に通ったということを、幼少の私はよく父から聞かされております。今日では豆腐は、肉の一枚にあたる高値でありますが、当時は最も安い部類の食品であったようです。月謝が支払えない父は、特待生の恩恵にあずかるべく、終始一番で学校を卒業しております。こうしたことは父の自慢話に聞いたものです。父の生き方、父の子どもに対する教育は、二宮尊徳を離れて考えられません。幼少から私たち兄妹は、毎朝神棚と先祖(仏壇)に手をあわせ、床の間にかけてあった掛け軸の文字を、読まされてからでないと、朝食にあずかれませんでした。私は字が読めない頃から、大きい兄たちと並ばされて、この掛け軸を読んでおります。掛け軸の文字は漢文であり、この意味などわかろうはずがありません。実はその掛け軸は「報徳訓」でした。私は何やら意味のわからぬまま、この報徳訓を暗話しております。
「ホウトククン フボノコンゲンハ テンチノレイメイニアリ……」
「二宮翁夜話」をご家訓として育った私は、生まれてはじめて学校の門をくぐった時、そこに二宮金次郎の銅像があったことに、何の不思議もありませんでした。それどころか大変親しい師が、銅像になっているのだなあと思ったほどです。少年二宮金次郎は、質素・倹約・勤勉、父母に孝に兄弟に友にのお手本でありました。
奉安殿と金次郎像
金次郎の銅像は、奉安殿と共に小学校時代の私たちに君臨しておりました。天皇・皇后の「御真影」が祭られていた奉安殿は、校庭の正門横の塚にあり、金次郎像は東門横のジャングルジムと並んでありました。当時は一棟しかなかった馬込第三小学校の校舎の、どの教室からもこの2つのシソボルは見えました。支配する者と、支配される者としての2つの精神的象徴は、具体的な形をもって、私たち子どもを圧倒しておりました。登校下校の時私たちは、奉安殿に最敬礼させられております。させられたというのではありません、ごく自然にそうしたのです。生徒が宿題を忘れたり、規律を破ると、教師は薪を背おわせて金次郎像の前に立たせます。薪でなく水の入ったバケツという時もありました。そして何と守らなければならない、多くの規則や規律があったことでしょう。金次郎像は、親しく幼年時代の私たちの血肉を作りました。幼年時代の体験が、どんなにかその人問のその後の人生を支配するか、影響をおよぼすかは、心理学者や精神医学者の言を待ちません。
柴刈り縄ない/わらじを作り/親の手助け/弟を世話し/兄弟仲よく/孝行つくせ/手本は二宮金次郎
今から思えば、決して詩的でないこの小学校唱歌を、私たちはうたいながら成長しました。国定教科書に登場するだけではなく、唱歌にまで金次郎が登場したというこの事実は、重大な意味を持っております。金次郎は、皇民化教育の、最も具体的で親しい先生となっていたからです。この土の思想家は、何よりも経済主義者であり実践論者であったことが、民衆の心をつかんだのでありましょう。第1期国定教科書令が公布されましたのは、1903年(明治36年)の4月です。この時から敗戦まで長い間金次郎は、日本の民衆の脳裏に、幼くして先生として焼きつけられました。
平民から出た偉人の役割
奈良本辰也『二宮尊徳』(岩波新書)は次のように申しております。「井上哲次郎は、国定教科書のなかに二宮尊徳が入れられたことについて次のようにいっている。『国定教科書に二宮翁を加へたるは、最も選の宜しきを待たるものと謂ふ可し。我国史中模範人物としては中江藤樹あり、貝原益軒あり、上杉鷹山あり、水戸の義公あり、烈公あり。共に是れ大和民族の精粋にして、後世の模範となすに足るべきものに相違なきも、鷹山、義公、烈公の如きは、何分大名なるが故に、一般平民に其縁頗る遠く、感化又或は及び難きものあり。独り二宮翁は然らず、翁は平民にして、而も農夫の子として成長せり。故に農家の子女には、其境遇近く、其境涯相似たり。境遇等しきが故に、教師は学びて怠らず、勉めて休まずんば、農家の子女も、亦能二宮翁の如くなり得べしとの希望を抱かしむるに足る』(井上哲次郎「学説上における二宮尊徳」留岡幸助編『二宮翁と諸家』所収)というのである。しかしこれをつぎの言葉と対照するとまことに面白い。それは、やはり同人の言葉であるが『余は一たび国定教科書中に吉田松陰を加へんと欲せしも或人之に反対して日く、精神は兎も角も、彼は時の政府に反対したるもの、小学生徒には終に不適当の人物たるを免れずと。是に於てか遂に松陰を加へざる事となれり。』(同上)まことに意味の深い選択であったといえよう。ここに、政府が尊徳を重んずる理由は顕然たるものがある。このようにして、身長6尺、体重25貫、激せば大藩の重臣をも小児の如くしかりつけて後にひかない、そうした男が、いつまでも16歳のかよわい少年の姿でとらえられ、勤・倹のみが彼を現わす代名詞のようにもなり、あの校庭に立った二宮金次郎の像が彼のすべてを象徴するようになったのであった。」
金次郎がどのような意味を持って、国民を導く立場にむかえられたか、教科書の編者自身がせきららに語っているではありませんか。太平洋戦争が激化し、菓子屋の店先きには「ほしがりません勝つまでは」という紙がはり出されました。子どもたちの生活までも根こそぎ「鬼畜米英」にむけられたのであります。そうしたなかで、私たちの先生二宮金次郎像は、プロソズであったために弁当箱やなべかまと一緒に、お国のために「出征」していきました。金次郎は大砲の弾になったのです。像になった金次郎も、実によい皇民であったわけです。長刀や竹槍をふりまわす私たち児童を見守る金次郎は、ブロンズから石像にかわりました。お国のために「銃後」を守っていた私たちは、東京空襲がはじまると、学童集団疎開をしました。
学童疎開と隆君の死
次の世を背おふべき身ぞたくましく、正しくのびよ里に移りて
皇后陛下の「聖歌」に送られて、私は5年生の春から6年生の秋まで静岡県の伊豆へ、そしてここでも空襲にあい、富山県の西礪波へ再疎開しました。敗戦は西礪波の寺でむかえております。子どもにとっての戦争とは何であったかは、私の学童疎開体験が如実に語ってくれますが、今はくわしくお伝えする余裕がございません。
疎開中、最高学年になった私は、教師の指導のもとに、下級生を統率してきました。当時教師の権威は絶対的でありました。日常生活の中で、金次郎の教えよろしく、教師の手を助け、弟や妹たちをよく世話しました。石ころがじゃがいもにみえ、ワカモト(薬)を空腹のためにたべてしまうような、食糧難でした。敗戦の年の夏、私たちが手あつく看護した3年生の隆君は、栄養失調と小児結核で疎開先きで死亡しました。寮母先生と交替で隆君を背おい、私は往復5キロの道を、寺から町の医者まで通いました。彼は次第にやせ細り、ミイラのようになって死んだのです。
「おかあさんにあいたい」と隆君は虫の息で私に申しました。生きていた隆君のぬくもりと、彼の最後の言葉「ありがとう」を、私は忘れません。
私は太平洋戦争で、肉親の一人を失っておりますが、隆君の死はその時受けた悲しみ以上のものでした。小さい生命に襲いかかる死への憎しみは、悲しみをとおりこした怒りとなって、その後の私の中に生きております。当時の私たちに「東京に帰りたい」「おかあさんにあいたい」という言葉は禁句でした。皇国少年、少女たちはよくこの規律を守ったのです。隆君のこの世での最後の言葉が、この禁句であったことが、私の心を大層しめつけました。
直接的には飢えが、大局的には戦局の深刻さが、私たちの心情を左右しておりました。隆君の死は、私たちに大きな翳りを落しました。次は自分の番ではないかということです。喜びや苦しさやひもじさを、共にしていた私たちです。隆君の死を、自分の一部の死と思いました。彼の死は敗戦直後のことでありましたが、権威に対する不信は、敗戦を待たずして子どもたちの中に不安となって、芽ばえてきていたのです。
隆君のおとうさんが、角の焼けこげた皮のトラソクを持って、息子の遺骨をむかえにきた時、私たち学童はどうしても隆君の骨を渡さないといって、はじめて教師に刃向かいました。子どもたちは友の骨をかかえて、布団部屋に龍城したのです。私たちは彼の骨をまじえて、誓いあいました。隆君と一緒に生きるのだ、隆君が東京に帰る時は、私たちも帰る時だと。生きたい生きたいと、必死で死と闘いながら死んでいった友の、奪い去られた生命のぶんを、私たちが生きぬくのだと誓いあったのです。
児童文学の道へ
少女時代の戦争体験が、私を児童文学の道に歩ませました。私はどんなに年をとっても、生きているかぎり子どもの側に身をおき子どもらの実存を、表現していきたいと思いました。それは子どもにとっての太平洋戦争とは何であったかに、はじまっております。子どもも一個の個性を持った人間存在です。彼らにとって、この世はどんな風に存在しているのでしょうか。子どもたちも社会に対して、子どもとしての希望を持ち、反発を持ち、あるいは喜びを持っているはずです。私はそれを表現していこうと思っております。このことが沢山の思いを残して、幼くして死んでいった隆君の心を生きることであると思いました。子どもは社会の仕組の中で、疏外されています。そして子どもは、大人たちに対して自己を防御しにくい存在でもあります。
奪われた教育権
大城俊雄さんは、隆君と同じ学年であります。彼は敗戦の年3年生であったと申しております。大城さんが幼年期にどのような教育を受けたか、それは私の経験と似ているのではないでしょうか。しかしさらに彼は、沖縄からの出かせぎの父母を持ち、差別と貧困の日常を強いられております。君に忠、親に孝、質素、倹約の二宮先生は、私たち以上に大城さんの幼い心をとらえたことは、信じるに疑いありません。同じ世代で同じような体験を持つ私は、彼の思いが体中で感じられます。
大城さんが「こんなもの子どもの役にたたん」といって金次郎像をたたき壊す時、彼は幼年時代の己の体に、ハンマーを打ちおろしているのであります。そして何よりも重大なことは、彼が戦争中の教育しか受けていないという事実でありましょう。大城さんは、3年生までしか学校に出ておりません。9歳にして公教育からほうり出されているのです。沖縄出身者の家庭に強いられている資質と差別を、想像しないわけにはいきません。沖縄出身者にむけられる巷に生きている迫害は、ぬくぬくと教育を受けてきた私たちには、想像を絶するものがありましょう。
戦後民主主義教育、あるいは義務教育は、彼のような子どもたちを見捨てていたところに、なりたっていたことを痛く反省させられます。大城さんは教育を受ける権利を、完全に剥奪されてきたのであります。このことへの反省なくして、彼の行為を論ずることはできません。子どもは社会に対して、両親に対して、自己を防御しにくい存在であることを、差別を身をもって体験してこられた大城さんは、よく理解しておりました。彼は手紙の中で次のように書いております。
「現在の社会組織にも絶望を覚えます。金次郎のように何んでもかんでも勉強して最高学府の教育を受けねば人間らしい豊かな生活に達せず天皇や支配者の、屍生贅にされる弱肉強食の組織にかぎりない悲しみといかり絶望を覚えます。ですから児童さんが<教育ママ>に虐待されているのです。」
「こんなものは役にたたん」
子どもが教育ママに虐待されているという、現実の子どもたちの声をまっすぐ聞きいれ、大城さんはこれを指摘しております。
敗戦は子どもたちに、何を教えたかと申しますと、大城さんのいう「こんなものは役にたたない」ということでした。母親の腹の中にいる時から、すなわち骨のずいから皇国思想で人間形成された私たちです。敗戦はこの肉をこの血を否定することでありました。大人たちのように、頭の切りかえができる軸など持たされておりませんでしたから。戦争下に自己形成をはじめていた私は、宇宙を支配していたこれまでの権威の崩壊を、目の当たりに見て、これまでの自己を全く否定することを迫られました。信ずるものは、自分以外になく、これから自分が創造していく以外にないということです。私たち疎開児童は、帰京すると二宮金次郎の石像を、自分たちの手で泣きながらこなごなに壊したのでした。この行為は、自分自身を鞭打つ行為だったのです。私は今、大城さんの行為に、27年前の私たちの姿を見たのでした。
実際教師たちは、これまでの日本の行為は植民地戦争であり侵略戦争であったと、否定すべきものであると私たちに教えました。民主主義というのは、みんなが参加してみんなで創造していくのだと、私たちほ学びました。民主主義は上から降ってこないということです。下から生まれてくるものであると。大城さんは9歳で学校を追われ、いわゆる戦後教育を受けておりません。このことは重要なことです。その後今日まで大城さんは、さまざまに迷いながら戦後を、孤独のうちに模索してきました。この間彼はどのような待遇で、どのような仕事にたずさわり、生活を維持してこられたでしょうか。このことも私はくわしくは存じません。
大城さん一家の苦難
大城さんのおかあさんは、若くして本土に渡り、紡績女工をして働いております。その後沖縄に帰って、おとうさんと結婚されました。やがて大城さんは3人兄弟の次男として、沖縄で生まれております。一家は職を求めて昭和16年本土に渡り、おとうさんは和歌山県で温泉の釜たきをはじめました。戦況の悪化と、戦時下経済は、釜たきの職をおとうさんから奪い、名古屋の焼け跡に出て、廃墟で養豚業をはじめたということです。生活が苦しく敗戦を迎えると、おかあさんは沖縄の実家へ戻りました。大城さんは貧困のなかで母に去られ、小学校は事実上3年で中退したと申しております。その後は長欠児童であり、やがて学籍簿すらも消されてしまうのです。
幼い大城さんが食べるために、倒れずに生きるために、どのようにさすらってきたか、彼は「私は業を背負って生きているようなものです」「私の歩んできた道は、到底人に理解してもらえないかもしれない」と手紙で書いております。戦時下の本土と沖縄の混乱の中で、大城さん兄弟は籍を入れられずにすぎ、やがて敗戦とそれにつぐ沖縄の分離下で、彼らは戸籍がないという状況のまま、今日をむかえております。おとうさん勇一氏の出身は、沖組県国頭郡今帰大字親泊であります。おかあさんマツさんは、幼い日の記憶をたどるとグシケンという所で、おかあさんの兄妹はグシケンでキイガヤ商店なる商いをしているということです。大城さんは、本籍はないが「わんやまくとぬうちなわんちゅうです=私は誠の沖組県人」と申しておられます。
戸籍がないので、パスポートがおりず、大城さんは故郷に帰りたくとも帰ることができませんでした。そして再会できぬまま昨年おかあさんを亡くしております。私は「おかあさんにあいたい」といって死んでいった隆君を、大城さんに見ました。彼は戸籍がないので、本工員として勤めることもできず、臨時工に甘んじなければなりませんでした。港湾、土木建設の労務者として、西に東に放浪しております。大城さんの個人生活は、戦後を迎えておりません。大城さんが「こんなものは子どもたちの役にたたない」といって金次郎像を打ち壊す時、彼は自らの手で戦後を創造しようとしているといえましょう。
低賃金で転々と渡り歩く大城さんの不幸は、私たちの歴史が沖縄県民に強いた、迫害の歴史でもあります。彼はあまりにもひどい待遇で今辞めてきた職場を後に、明日の職をどこに求めていくか考えながら、ふと足を戸板小学校にむけました。正面玄関横に、大城さんは彼の不幸を形成した二宮金次郎の亡霊を見たのです。この時大城さんは一瞬にして、幼少期を思いおこしたことでしょう。一瞬にして戦後28年の地獄をはうような、生活を思いおこしたことでしょう。大城さんが金次郎像を壊す時、子ども時代に犠牲しか払わなかった戦争責任を追及しているのです。当時は私たちは被害者でした。しかし現在は歴史に、社会に責任を持っております。
事件の動機
大城さんは手紙で、事件の動機を次のように申しております。「事件の当日は紅葉の秋です。もみじのような可愛らしき手をした幼なき子供さんに、大なる夢を託し重き荷を背負わせるのは、信仰上又は道徳上許しがたき義憤を覚えた訳に、存じますが―」「私は我が身をかえり見て学校当局に望みますのは過去のような矛盾した教育ではなく勝手に大人の考え方を幼い心に吹きこみ重荷を背負せないで子供は平和に生きる道を自らの手でえらび平和を求め行く権利をおてびきして下さるよう学校当局に望みます。ですから<道具衆>としてかつぎだされた<金次郎像>が今日もなお校庭に放置されて居るのは矛盾してふさわしく思えません。第二次大戦では大人の争いや戦いに子供をまきこんだり戦いの道づれにしたのですからその死を悼み永遠にざんげする意味にても<二宮像>を撤去してそれぞれの学校当局の児童犠牲者を校庭に建立したほうが真の平和を求める姿ではなかろうかと考えます。ちなみに小豆島の<二十四の瞳像><沖縄の健児の塔><ひめゆりの塔>などが大人の争や戦いに子供をまきこんだ責任を感じさせ戦争防止に役立のではなかろうかと考えてのこのたびの事件で御座居ます。」
そして大城さんは、親戚のおばあさん一家に想いをはせておりました。「近卑な一例を取りましても沖縄に住居する私の親戚のおばあさん一家は5人の男子の子宝に恵まれ乍ら第2次大戦で鉄の規律で5人の息子を奪われ、戦いにかりだされ、壮烈戦死の犠牲を被ており、そして何んの報くわれることも、戦争責任者である天皇を遺恨と憎しみの中に死んだとの風の便りです。」
沖縄の子どもたち
私の学童疎開中の日記(1945年7月1日)には「きょう寮長先生のごくんわに、沖なわの赤国民学校の生徒ぜんいんが、手りゆうだんをもって、敵じんにのりこんでいったと、しんぶんにはうどうされたことをおっしゃいました。私は沖なわの生徒はりっばだと思いました。私はなみだがでてきました。私もがんばりたいといっしょうけんめいに思いました」と書いてあります。
今次大戦の沖縄決戦で、沖縄の子どもたちがどのような運命と犠牲を強いられたか、これまた本土の子どもとは比較にならないものがあります。私は大城さんが沖絶県出身であることに、深い痛みと反省を覚えます。彼の行為は私への、とりわけ子どもの文学にたずさわる者にむけられた糾弾として、受けとめております。
言語道断の行為
本件の告訴人は、岡良一氏名義の金沢市長になっております。告訴状は次のようなものでした。「昭和47年3月2日午後4時20分ごろ、金沢市立戸坂小学校前庭において二宮尊徳(陶製)を理由もなく乱打破壊したことは言語道断の行為であり、尊敬する立像を失った児童の精神的影響は極めて大であるため、調査のうえ処罰願います。」
大城さんが金次郎像を乱打破壊したことは事実であり、彼もこれを認めております。彼の行為には深い動機と理由があったことを、私はこれまでに申し上げてきました。被告人にとっては、表現不可能なほどの、いいつくせぬ理由がありました。しかし私たちの生活する法社会では、破壊行為は非難されるものとなっております。百歩ゆずってそれを受け入れても、被壊せざるを得ない歴史的背景を考えますと、どちらが重たいものでしょうか。答えは明白だと思います。取りかえしのつかない無惨な犠牲のうえに得た28年前の尊い教訓を、被告人は破壊という行為において、金次郎像が象徴している思想にむけたのです。
子どもたちに死の犠牲を強い、子どもたちにとって侵略戦争のシンボルでありました二宮金次郎像が、市内の小学校校庭にあること自体が、反省されるべきことと思います。戦中からひきつづき建ちつづける金次郎像を擁護することは、赤国民学校児童や無数の隆君の死を歓迎することであります。侵略戦争を掩護することであります。
奴隷の思想
もともと二宮尊徳の思想は、金次郎に象徴されるもののみではなかったでしょう。しかし問題は、尊徳という経験主義者は、天下国家の大勢も運命も考えなかったことにあります。彼には政治批判がまったくありません。そのことが国民学校児童や、無数の隆君の死を歓迎することになったのです。二宮のいう勤勉と従順は、奴隷の思想でありましょう。権力を持つ者には、都合のよいことに違いありません。尊徳は「貧にして富之非を見出し喧譏するものは不仁なり」(『農家大道鏡』)と書いております。農民一揆は、農民の方に責任があるということのようです。また尊徳は「知足安分」といって、百姓は百姓、工人は工人として分に応じた生活をせよと申しております。身分制度という階級制度を擁護しているのです。時代が時代だったからという理解の仕方はありますが、それと評価とは別の次元で語られなければならないでしょう。ところが尊徳自身は、努力に努力を重ね、農を脱出して士になっております。身分制度の厳しい徳川時代に、これは全く信じられないようなことですが、そこにはこれまた信じられないような力行がありました。
告訴状は「言語道断の行為」と、確信を持って申され、「尊敬する立像を失った児童の精神的影響は極めて大である」と述べております。果たして金次郎像が、今日の子どもたちの尊敬の立像となっておりますでしょうか。もしそうだとすると、それは恐しいことです。何故なら「いつかきた道」ですから。
敗戦直後GHQでは、「教育上よろしくない」という意向で、金次郎像を取り払うようアドバイスをしております。GHQの教育担当者が、各県に出むいて指導をしておりますが、地城によりまた担当者の姿勢により、まちまちであったようです。取り払われなかった地方もかなりありました。東京では徹底的に取り払われ、民主化の模範を示したということです。
子どもたちの受けとめ
現実に今日の子どもたちが、金次郎像を尊敬しているかどうかと申しますと、はっきり言って尊敬もしておりませんし、関心も持っておりません。芸術作品としても美的とはいえないこの像に、関心を持つ子どもは、次のように評価しています。
「この子、交通事故を起こすよ、あぶないよ。この子、目が悪くなるよ。」などであります。この意見が金次郎像からうける、子どもたちの偽りのない言葉です。子どもたちは今のところ金次郎像の持つ思想を、現代的には非合理なものとしてしか、受けとめておりません。しかしそれはあくまでも今のところであります。支配者が意識的に都合のよい金次郎の思想を、子どもたちへ吹き込むことは可能です。そしてこれまで金次郎が登場する場面は、必ず社会不安や内外の情勢の厳しい時でありました。国民に不平をいわさず、しっかりおさえておく必要のある時でした。
教育勅語と道徳教育
すでにふれましたが、国定教科書令が公布されたのは、1903年であります。この年から画一化された教科書が、全国で使用されるようになりました。金次郎はここにおいて、全国のどのような辺地の子どもたちの前にも、登場するのであります。(1900年、義務教育4年制、1907年、義務教育6年制となる)ところが、これより先き1886年(明治19年)に臨時修史局が設置され、教科書検定条令が公布されました。明治19年に、国定教科書が始まったとみていいでしょう。先きに述べました井上哲次郎の頭の中には、この時金次郎がのぼっておりました。そして明治政府は、1889年(明治22年)に従4位の位を、尊徳に贈っております。彼はここで明治維新に功労のあった元勲たちと肩を並べるのでした。何て意図的なことでしょう。
明治22年という年は、大日本帝国憲法が発布され、その翌年には教育勅語が発布されました。立憲政治は、権利に目覚めた「市民」をいやおうなくつくりだします。為政者はそれに呼応して「臣民」としての心構えを明らかにしておく必要がありました。教育勅語は、権力操作のために、天皇親政の徹底化としてでてきました。教育勅語こそ、道徳教育の基本でありましょう。
二宮金次郎が教科書に登場したのと、二宮尊徳が政治上のテコとして、積極的に支配者に利用されはじめたのは、軌を一にしております。1905年11月、日露戦争の直後、二宮尊徳50年祭が、政府の手で行われました。この50年祭を機縁として、内務省、農商務省の官僚が中心となり「報徳会」を結成しました。「報徳会」は政府の地方改良運動の理念的範型となったものでした。報徳会運動は、日露戦争後の社会不安と、内外の情勢の緊迫化の中で進められました。『日本の百年』7巻「明治の栄光」(筑摩書房)によりますと、報徳会結成に参加した顔ぶれを、次のように伝えています。
「内務・農商務官僚のほか、地主、篤農家、郡長、村長、村役場書記、師範学校、小学校長、僧侶、産業組合役員、銀行、会社重役等々いわば日本社会の底辺を支える地方指導者を網羅していた。山路愛山が<日本帝国の4本柱>と呼んだ村役人、学校の先生、寺の坊主、駐在所の巡査のうち、巡査をのぞいた各層の代表者が集まり、その周辺に桑田熊蔵、神戸正雄、内田銀蔵らの学者達も動員されるというかたちをとった。」
さらに同書は、「報徳会は、尊徳の遺訓とされた4原則―至誠・勤勉・分度・推譲の徳目にもとづいて、社会調和をはかろうとする官民有志の組織であった。その場合、会の主体となるのは地方名望家であり、彼らの指導性を再編することによって、予想される階級対立の激化、社会問題の蔓延を阻止しょうとするものであった。そのため内務官僚たちは、地方名望家層の実情を正確に把捉しょうとつとめた。」といっております。報徳社のねらいは、さらに次のようなところにもありました。
「従来のように郡役所の若い役人が地方の名望家である村長を監督するのではなく、自治を奨励しながら教えを導いてゆく、すなわち指導するということにあった。」(石田雄『明治政治思想史研究』の聞き書き)
国づくり、人づくりの手本
日露戦争後の社会矛盾を克服するために、内務官僚によって推進されました新しい国づくり、人づくりの手本として、二宮尊徳の思想は恰好でありました。民衆は支配者に逆らわず分をわきまえ、農村の矛盾(疲弊)をひたすら努力によって、すなわち勤勉と倹約で解決していくよう導かれたのです。二宮尊徳の「勤・倹・譲」は道徳的な経済生活であります。勤は勤勉であり、一生懸命働くことでした。倹は倹約をすること、譲とは推譲のことで譲道があってはじめて人間の社会がなりたっているとしました。尊徳は申しております。「親にも朋友にも譲らずばあるべからず、村里にも譲らずばあるべからず、国家にも譲らずばあるべからず。」(「夜話」)
ところで尊徳の譲とは、藩を建てなおし、幕府の困窮を救うものとしてありました。そして確かに彼は、その力を発揮しております。彼は貧しい人びとにも、しばしば救いの手をさしのべておりますが、それは彼らを「勤」に奮起させるための奨励金としてです。貧窮の根元である矛盾を正さずに、それをとりつくろうことに全力が傾けられるのでした。
明治の天皇制国家が、彼をして民衆の心をとらえようとした意図を、察することができます。赤貧洗うがごとき貧乏から、努力に努力を重ねて、国のためにつくしたという二宮先生は、貧しい民衆のアイドルになりました。貧乏でも高い地位や名誉がなくとも、十分お国のためになれると、民衆を導くことは、為政者にとって結構なことに違いありません。くりかえしますが、義務教育下の国定教科書によって二宮先生の教えは、全国津々浦々の子どもたちの脳裏にやきつきました。そしてまた実生活では、報徳会が全国的に活躍しております。
二宮金次郎の亡霊
こうした歴史経過を考えあわせますと、これまで放置されておりました金次郎像が、法廷にまで引っはり出されて来たこと自体に、ただならぬ不安を感じるのであります。教科書の反動化が法廷で論じられ、争われている今日、子どもの側に身をおくことに自己を律し、子どもの文化創造を仕事にしている私たちにとって、金次郎像をめぐる今回の事件に、ロをつぐんでいるわけにはいきませんでした。
アメリカ経済の危機の現われであるドルの低落は、国際資本の圧力を円にもたらしています。経済のことはよく理解できませんが、円の変動相場制は、日本経済の虚弱体質の破れ目ではないでしょうか。消費文化の見せかけだけの繁栄は、目の前に大きな動揺が待っていることを、私たちにひしひしと感じさせます。二宮金次郎の「勤・倹・譲」が動員される危惧をいだくのは、ひとり私だけではないと思います。
「交通事故にあわない、目が悪くならない」時代にかなった金次郎が、現われてこないともかぎりません。経済状況の行きづまり、インフレによる物価高、子殺しをする親が次々と現われ、公害に対する市民の怒りが結集しております社会情勢であります。
器物損壊という罪名で、4カ月近くも大城さんの身柄を拘束し、なおかつ50万円の保釈金ということに、私は驚きをかくせません。建立当時(昭和初期)、金次郎像は5円か10円であったそうであります。戸板小学校長が、教育委員会に提出した報告書には「時価1万3000円」とあり、検察官の起訴状には「時価10万円」となっております。検察官にはインフレを促進している傾向がみられます。検察官はもしや二宮金次郎像に、精神的思想的「高価」を計算しているのではないでしょうか。ここに二宮金次郎の亡霊が、大手をふって生きていることがわかります。
今回の大城さんの行為によって、私は太平洋戦争で死んでいった子どもたち、とりわけ私の記憶のひだにたたまれた隆君や、沖縄の赤国民学校の児童たちのことを思いおこし、胸をかきむしられております。
世界の良心と民主主義
裁判長さま、私はあなたの真理にかなった民主的なお裁きを、二宮金次郎によって自己を形成し、且つ死んでいった無数の子どもたちと共に見守りたいと思います。かつて東京裁判の際、キーナン検事は「原告は世界の良心と民主主義である」と申されました。本件の告訴者は、金沢市長でありますが、お裁きになりますあなたさまは「世界の良心と民主主義」をもって、お裁き下さいますよう、あえてお願い申しあげます。
以上
注:小見出しは当会が付けた。漢数字はアラビア数字に、誤字は補正し、引用文の改行も適宜おこない、読みやすくした。大城俊雄さんに関する原資料を保管していたのだが、長い年月の過程ですべて失ってしまった。金次郎像破壊事件は柴田道子さんの上申書と渡久地政司さんのHP(富村順一さんら救援活動)に依るしかない。